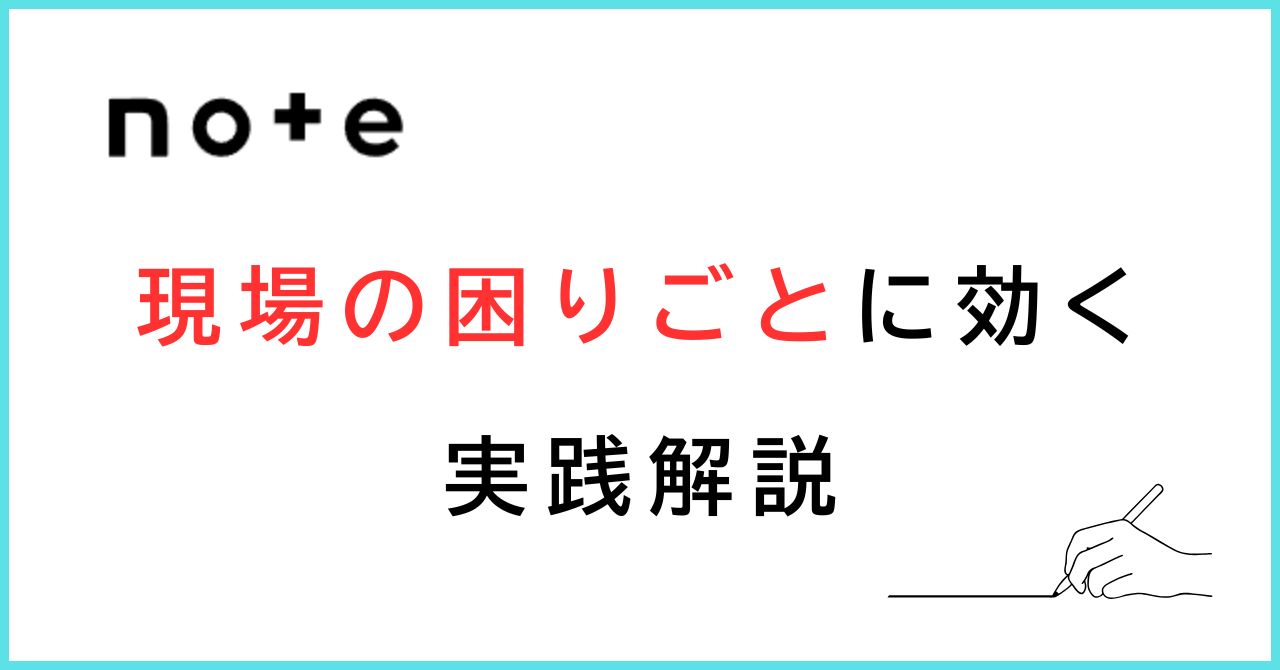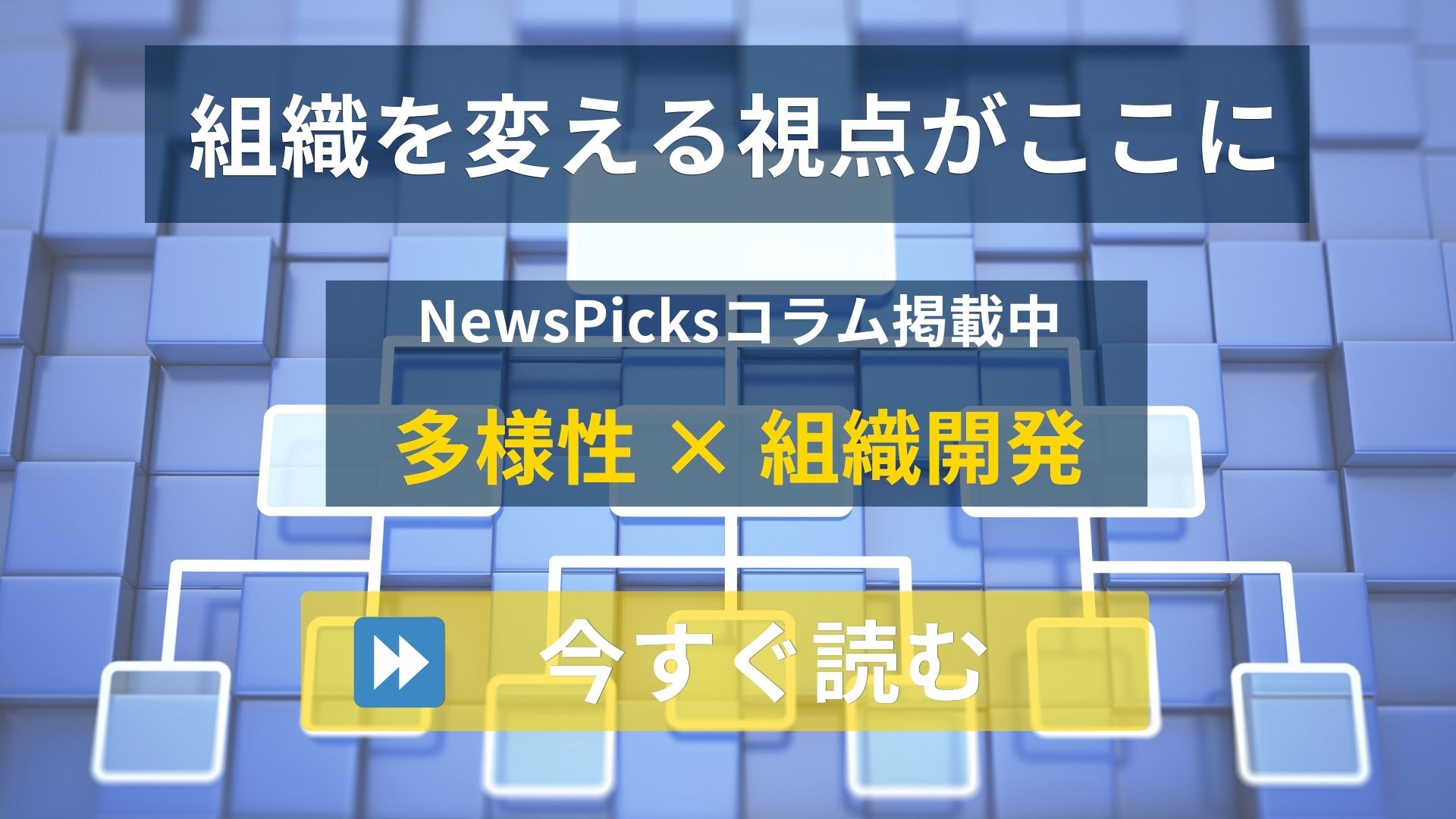専門分野のある障害者採用に役立つ国立リハとは?訓練内容を紹介
障害者雇用で困っている企業の中には、専門的な知識がある求職者であれば、採用を前向きに考えたいという人事担当者の人にお会いすることがあります。ハローワークの合同面接会に行ったり、支援機関を訪問しているものの、なかなか希望する人材に出会えないようです。 そんなときには、国立職業リハビリテーションセンター(国リハ)の訓練を受けた障害者の採用を検討することができるかもしれません。ここでは、国リハが行っている事業や障害者支援として行っているコース内容などについて説明していきます。 国立職業リハビリテーションセンターとは...