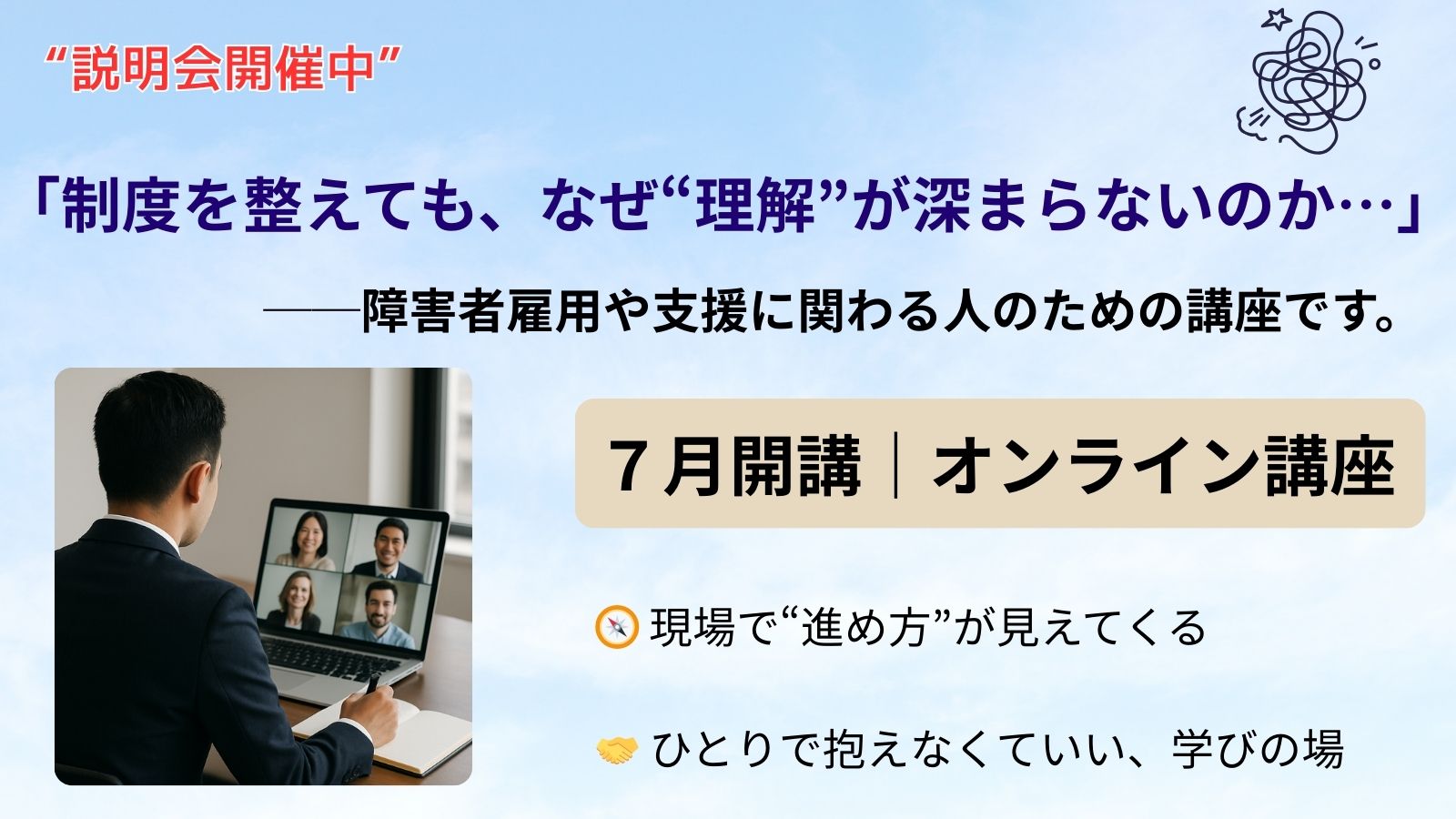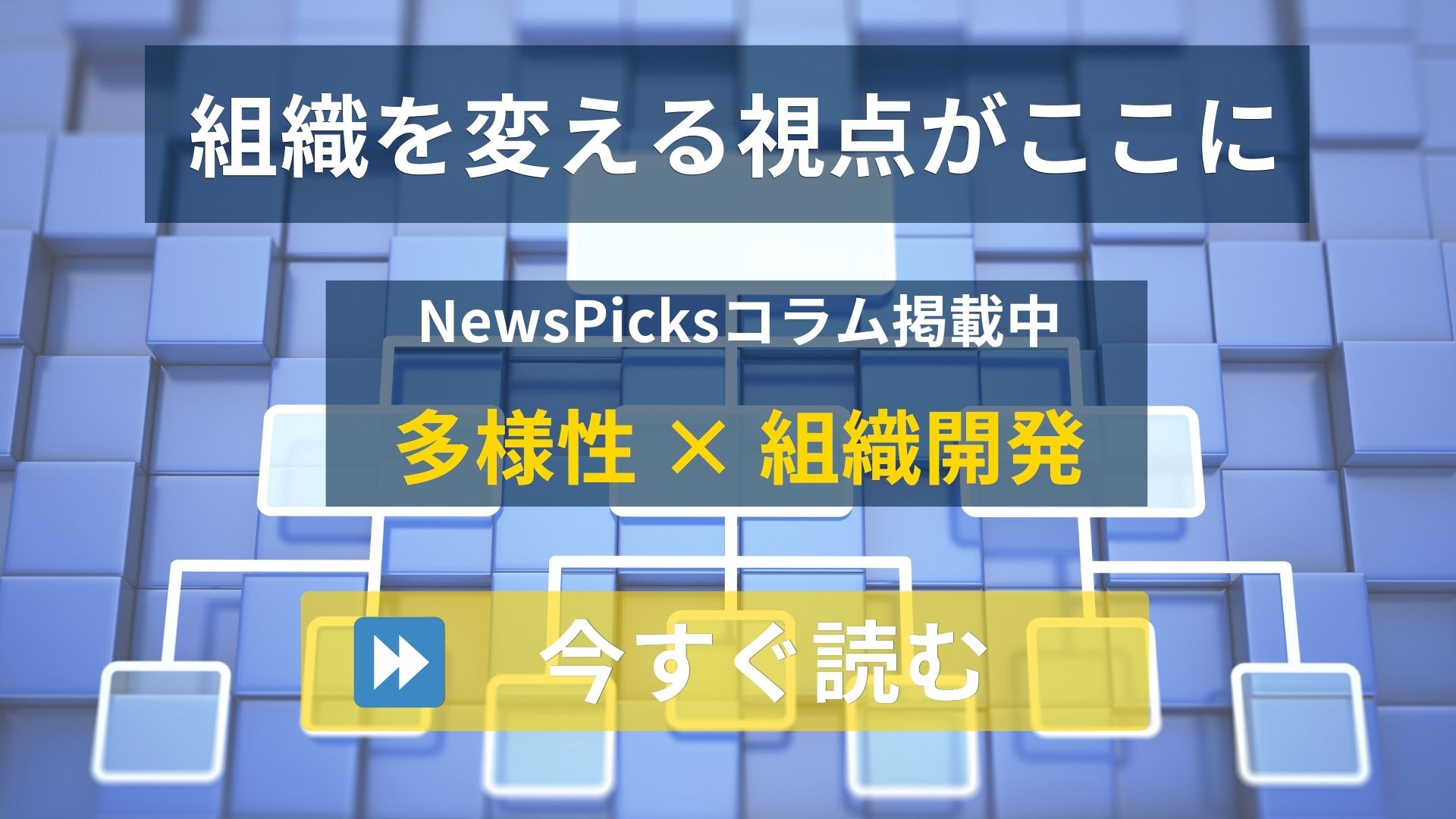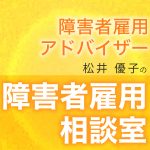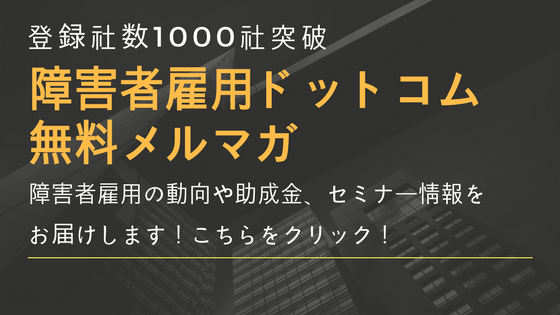会社の障害者雇用、一緒に働く社員に何を伝えたらよい?3つのポイント解説
障害者雇用を進めていくには、障害者への配慮を考えていくとともに、同じ職場にいる社員にも障害者雇用をすることの意義や、不安に思っていることなどについて伝えておくことが大切です。そうしないと、配属先の社員からの理解と協力を得ることができず、障害者の職場適応や定着につながらないからです。 障害者雇用をすることが決まった時に、障害者を配属する前に伝えておきたい障害者雇用の理解を得るためのポイントを紹介します。 ポイント1:障害の特性、配慮事項などを伝える...