障害者雇用は「雇用」です。そのため福祉や教育とは異なり、求められる仕事や業務ができる人を採用して、組織に貢献してもらうことが大切です。一方で、障害のために何らかの困難さや不都合さを感じており、それに対する配慮を求めていることが多くなっています。
そのため障害者雇用では、合理的配慮を示すことが求められています。しかし、当事者から予想外の配慮を求められたら、どの程度まで合理的配慮を示すべきなのでしょうか。
今回は、「今以上の合理的配慮はできない」と雇止めした企業に対して、元従業員が労働審判を申し立てた例から考えていきたいと思います。
障害者雇用枠で採用されたのに・・・
障害者雇用枠で保険会社に勤めていた元従業員の女性のAさんが、「障害を理由にした雇い止めは無効」として、会社に対し地位確認や損失補償などを求める労働審判を申し立てました。
Aさんは採用応募にあたり、配慮してほしい合理的配慮について記載し、その資料の中には「アクシデントが起きると不安感が高まりパニックとなりやすい」など、配慮すべき事項も記載されていたそうです。
しかし、Aさんは高温で地下の作業場で働いていたときにパニック発作を起こし、痙攣状態になりました。会社の人事責任者は、発作の原因は「てんかん」だとして、Aさんに脳外科の診断書の提出を求めます。
検査でAさんは「脳の異常はない」との診断を受け、会社に診断書を提出しました。これに対して、Aさん本人や産業医との面談も行わずに「2か月から3か月休職するように」と会社側から命令を受けたそうです。
Aさんは主治医の診断書として「勤務内容の事前の通知や休憩時間の確保、空調・冷房設備の整備などの合理的配慮が整い次第、即日復職が可能」と提出します。しかし、会社側は「今以上の合理的配慮はできない」「同じ条件で、また発作を起こす懸念がある」と判断して復職願は受け取らず、その後、Aさんは約半年後に雇用期限満了となる通知を受け取りました。
また、雇用期限満了前にAさんは「復職並びに雇用契約期間の終了」通知を受け、あらためて復職願を提出します。産業医との面談を受けて復職するものの、半月後に雇い止め通告を受けました。
Aさんは労働組合に加入し、3度にわたり団体交渉を行いましたが、会社の判断は「休職命令も雇い止めも本人の安全配慮のためだ」という主張でした。今回の申し立てでは、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、無効な休業命令による損失補償、無効な雇い止め後の未払賃金などを会社側に請求しています。
出典:「障害者雇用枠で採用したのに、障害を理由に雇い止めするのは違法」 元従業員が会社に対し約200万円を請求(弁護士JP)
企業では、障害者雇用を行う際に、合理的配慮を示すことが求められています。この合理的配慮とはどのようなものなのか見ていきます。
合理的配慮とは?
障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)」では、2016年4月から、企業で雇用している、またはこれから採用する障害者に対して合理的配慮の提供が法的義務となっています。
「合理的配慮」とは、障害がある人とない人の就労機会や待遇を平等に確保し、障害者が能力を発揮するために支障となっている状況を改善したり、調整したりすることです。なお、対象となる範囲は、事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象となっています。また、対象となる障害者は、障害者手帳を持っている方に限定されず、いわゆる3障害(身体障害、知的障害、精神障害)以外にも心身の機能に障害があり、長期にわたって職業生活に相当の制限を受け、職業生活を営むことが著しく困難な人も対象となります。
この法律の改正では、事業主に3つの義務が課されました。それは、次の点です。
・雇用の分野での障害者差別の禁止
・雇用の分野での合理的配慮の提供義務
・相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助
障害者差別の禁止という点では、障害者であることを理由として、そのほかの人と不当な差別的取扱いをすることが禁止されています。 例えば、募集・採用や賃金、配置や昇進、教育訓練など雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由に排除することや不利な条件を設けること、反対に障害のない人を優先することなどは、障害者であることを理由とする差別に該当します。
しかし、積極的な差別是正措置として障害者を有利に取り扱うようなこと、例えば、障害者のみを対象とする障害者枠の求人を行うことは、これに該当しません。また、合理的配慮を提供し、労働能力などを適正に評価した結果として障害者ではない人と異なる取扱いをすることや、合理的配慮に応じた措置をとることで結果的に、障害者ではない人と異なる取扱いとなることも該当しません。例えば、障害者が研修内容を理解できるように合理的配慮として独自メニューの研修をすることなどは該当しないことになります。
合理的配慮の提供の義務は、障害のある人とない人の就労機会や待遇を平等に確保し、障害者が能力を発揮するうえで支障となっている状況を改善したり、調整したりすることです。
障害の種類によっては、就業にどのような支障があり、どのような配慮が必要なのかが、見た目だけではわからない場合があります。また、障害の種類や障害者手帳の等級が同じ場合であっても、一人ひとりの状態や考え方、職場環境などによって求められる配慮も異なります。そのためどのような合理的配慮が必要なのか、企業側で取るべき対応については、一概にこの障害だからこれが必要と言えるものではなく、個別性が高いものとなっています。
そのため合理的配慮の具体的事例については、厚生労働省の「合理的配慮指針事例集」などで参考にすることはできますが、具体的にどのような措置をとるかについては、障害者と事業主とでよく話しあった上で決めることが求められています。
企業は合理的配慮を全て示さなければならないのか?
企業は合理的配慮を示すことが求められていますが、合理的配慮の提供にあたって、企業が果たすべき義務と障害者の権利のバランスをどのように取るかは重要な課題となります。合理的配慮は、企業が無制限に対応を行わなければならないというものではありません。企業が過重な負担を被らない範囲で合理的に実施するものであり、そのため「過度の負担」に当たるときには免除されることになっています。
合理的配慮の「過重な負担」には、次の項目が該当します。
・事業活動への影響の程度
・実現困難度
・費用負担の程度
・企業の規模
・企業の財務状況
・公的支援の有無
企業が提供する配慮が経済的・技術的に実施不可能である、または著しい負担を企業に強いるような場合には、企業はその負担の軽減策や他の配慮方法を検討することが求められます。
一方で、障害者は合理的配慮を受ける権利を有し、その権利を行使できることが保障されています。このバランスを取るために、企業は事前に障害者のニーズを把握し、配慮を提供するための具体的な手続きを整備することが必要です。また、障害者本人とのコミュニケーションを図り、企業側が合理的にできる限りの対応をすることが、障害者の労働環境を改善し、雇用の安定につながることになります。
意見の相違をなくすためにできること
障害者を採用してから求められる合理的配慮を示すことが難しかったり、企業での対応ができない場合にトラブルになりやすくなります。このようなことを避けるために何ができるのかを見ていきます。
採用時に求める合理的配慮の確認をする
合理的配慮の基本的な考え方は、障害者から事業主である企業に対して、職場で示してほしい配慮を申し出て、企業側が検討するという流れになります。多くの場合、申し出は募集や採用のタイミングで行われますが、障害者当人が支障を感じる状況が生じた場合には雇用後にも行います。
申し出があった場合には、どのような合理的配慮を企業が提供するかについて、当事者である障害者と企業の間でよく話しあいます。もし、本人が求める合理的配慮がうまく伝えられないような場合には、支援機関の担当者等に同席してもらうことなどもできます。
また、合理的配慮として取り決めたことについては、それを遂行できるように環境を整えることも大切です。障害者本人の意向を踏まえた上で、一緒に働く上司や同僚に、障害の特性と配慮事項について伝えておくとよいでしょう。一緒に働く人たちもどのような配慮が必要なのかを知らなければ、その配慮を示すことができないからです。ただし、障害に関する内容や知らせる対象の範囲などについては、障害者本人の意向を確認し、十分に打ち合わせしておくことが大切です。
本人から申し出があった合理的配慮でも、内容によっては企業がすぐに対応できないこともあります。もし、企業にとって「過重な負担」となるような場合には、その難しい理由を本人に説明するようにします。
合理的配慮の具体的事例については、厚生労働省の「合理的配慮指針事例集」「障害者への合理的配慮好事例集」「障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関する Q&A」で知ることができます。参考にしてみてください。
企業で配慮できることを伝えておく
合理的配慮の「過重な負担」などを検討しながら、企業でも合理的配慮としてできることと、難しいことをある程度想定しておくことが大切です。職場で合理的配慮として提供できることや、すでに雇用している障害者に対して行っている合理的配慮などを示しておくとよいでしょう。
また、採用時にはとくに希望がなくても雇用後に何らかの要望が出てくるケースも見受けられます。採用時の面接で、本人から申し出がない場合でも、障害特性やどのようなことが予想されそうなのかを「希望を聞く」というスタンスでヒアリングしたり、確認したりすることもできるかもしれません。
障害者が働きやすい職場にするためには、当人と企業がお互いによくコミュニケーションを取ることが必要です。企業側がよかれと思って行ったことでも、一方的な配慮ではかえって逆効果になることもあります。話し合いながら、本人の意向をよく汲み取って進めていくようにしてください。
リスク管理対策をしておく
合理的配慮の義務は企業にとって法的な責任であり、これを怠ることは法令違反となりうるため、法的リスクを軽減するためにも適切な対応が求められます。また、企業は配慮を提供する際に、その内容や範囲について障害者本人と十分な対話を行い、どのような支援が必要かを理解することが重要です。
合理的配慮について話をする機会としては、採用面接時が多くなります。しかし、障害者本人に合理的配慮についての知識があり、企業へ伝える準備ができている場合ばかりではありません。そのようなケースも想定し、企業側は面接のときに、質問や会話を通して障害特性や状況等を把握しておくことができます。
また、面接だけでなく、実際に実習など採用予定の職場環境で実際に業務する様子を体験することで、企業が考えていることと障害当時者の考えていることの相違を減らすことができます。企業側からすると、いつもいる職場で「当たり前」と思っていることが、外部の人には当たり前ではないことがよくあります。
労働問題に発展すると、企業での社外的な評価や、社内での障害者雇用を進めることに対する消極的な考えや雰囲気が強くなるというマイナス面がでてきてしまいます。合理的配慮は大切ですが、採用前に企業が求める能力やスキルなどをクリアしているのかを判断することが必要です。これには、体力やメンタルなども含まれます。また、労働問題になりそうな場合には、早めに社労士に相談するとよいでしょう。
まとめ
障害者雇用における合理的配慮の重要性と、それに伴う企業の法的責任について考えてきました。今回の事例は、当事者側の主張を中心に見てきたので、実際には企業側がどのような配慮や対応をしてきたのかについてはわからない部分があります。しかし、このような労働問題に発展すると、社内外においてマイナス面がでてきてしまいます。バランスをとりつつ、考えていくことが大切です。
合理的配慮は、障害者が職場で能力を最大限に発揮し、平等な機会を享受するための重要な手段です。しかし、それを適切に実施するには、企業が障害者との対話を重視し、個々のニーズに対応した配慮を行うことが求められます。
一方で、企業が配慮すべき範囲は無制限ではなく、「過重な負担」となった場合には合理的配慮の義務が免除されることもあります。企業にとって重要なのは、合理的配慮の内容や限界を事前に明確にし、障害者とのコミュニケーションを通じてお互いに納得のいく解決策を見つけることです。
企業側が配慮していると思っていたり、よかれと思っての行動していても、障害当事者に伝わっていないとトラブルになることがあります。一方的に配慮をすることは、かえって逆効果になることもあるので、よくコミュニケーションを図り、当事者本人の意向をよく汲み取って進めることが大切です。
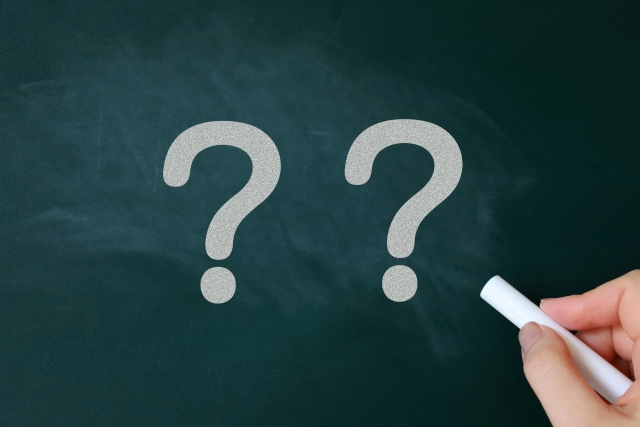






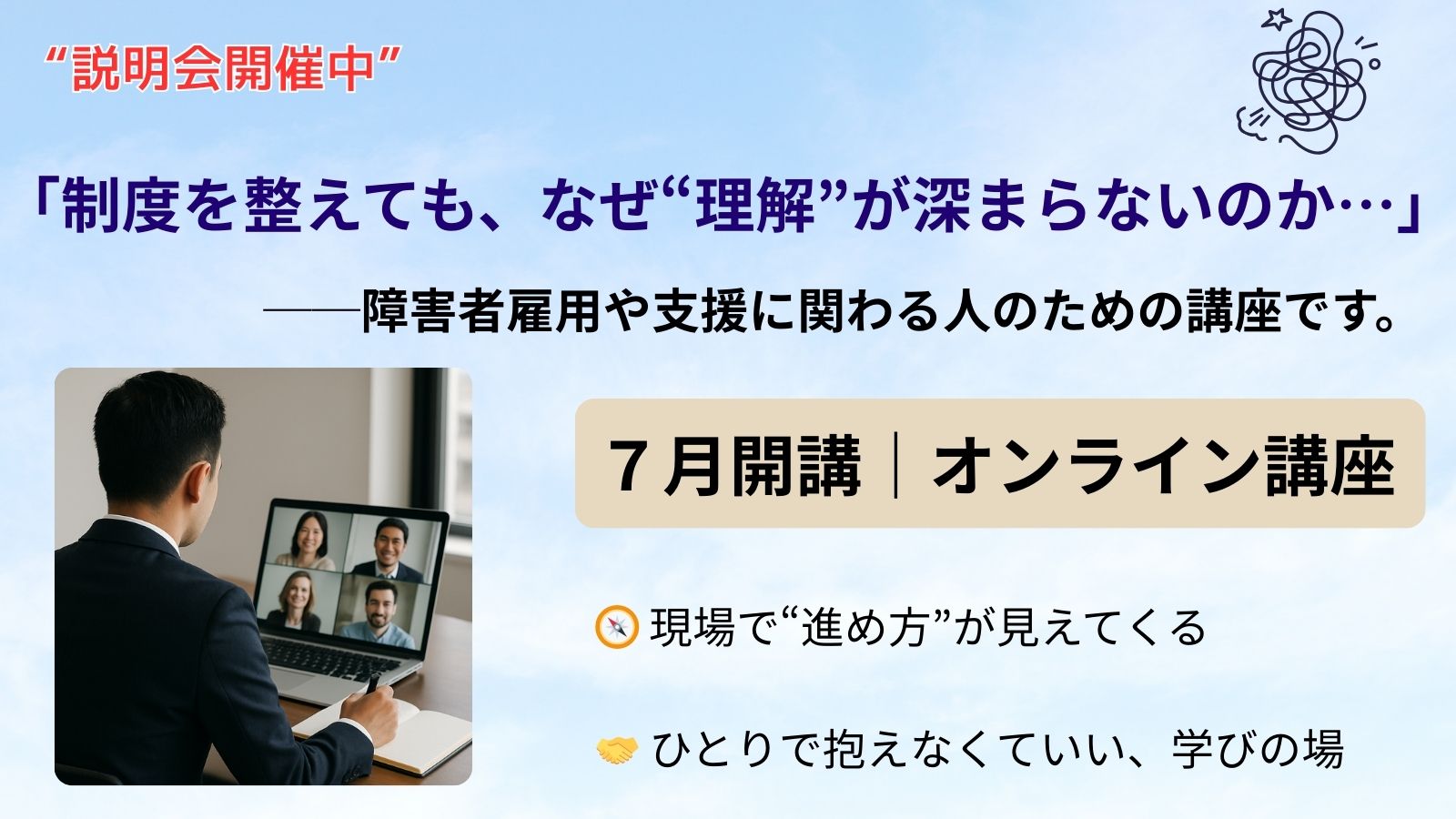

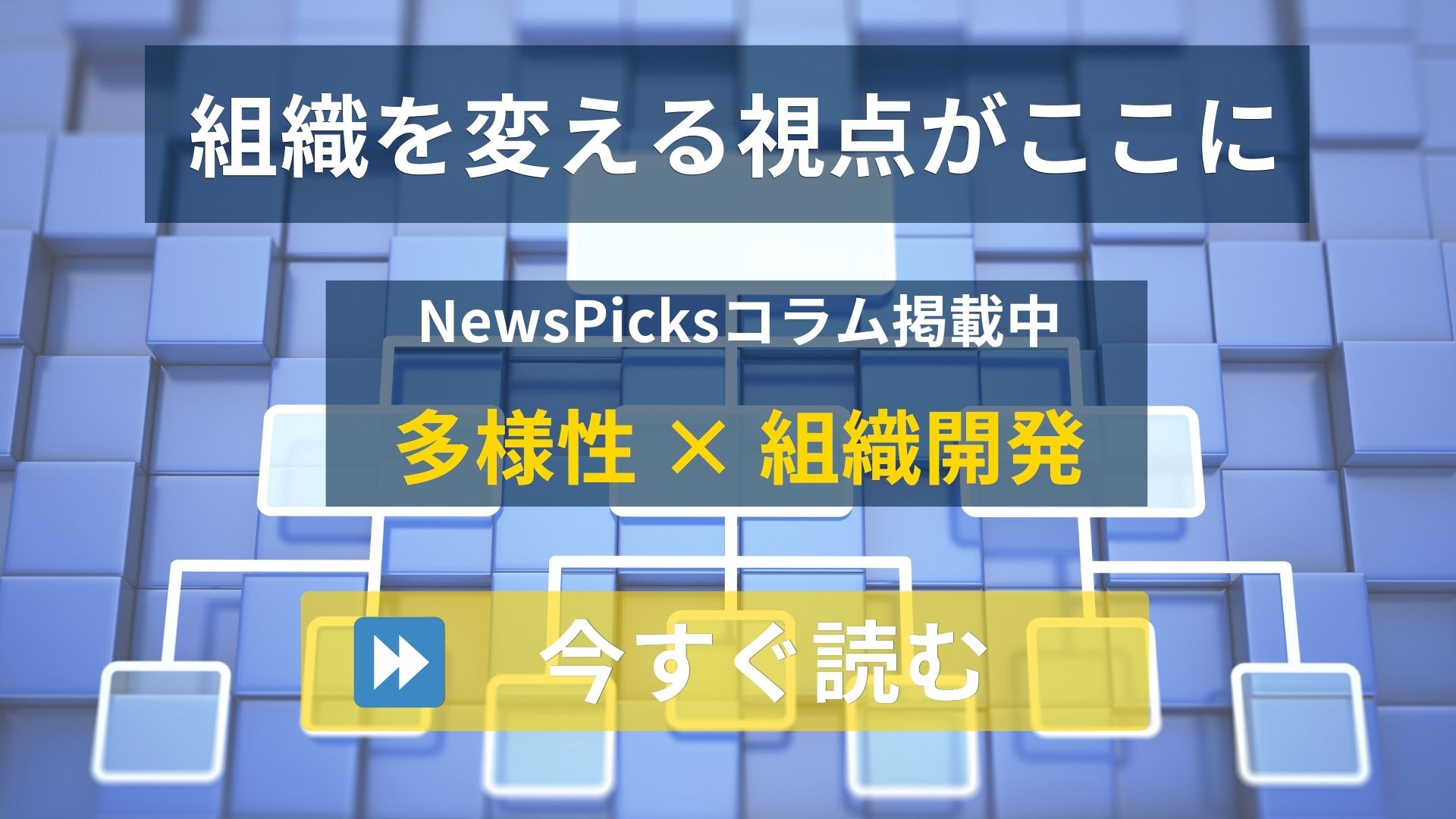


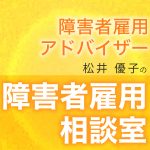

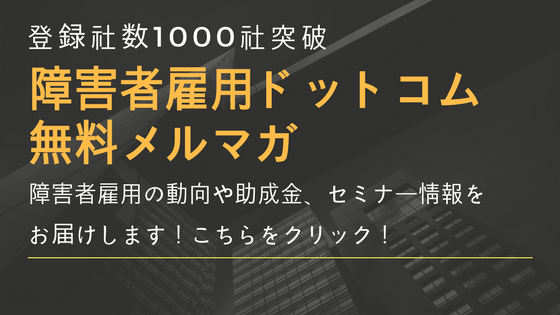










0コメント