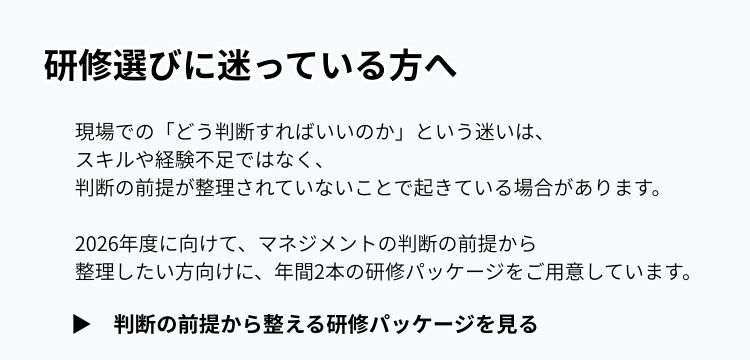職場のメンタルヘルスを学んで自分を守るために知っておくべきこと
近年の社会情勢、労働環境の急激な変化に伴い、多くの働く人が仕事や職業生活に強い不安やストレスを感じているといわれています。 働く人の心の健康であるメンタルヘルスを維持して、誰もがいきいきと働ける職場づくりを実現するために、また、自分を守るためにメンタルヘルスやメンタルヘルスに関する法律を知っておくことは大切です。 メンタルヘルスとは 「メンタルヘルス」、それは「心の健康」のことです。身体の健康が大切なのはもちろん、心も元気であることは、仕事を進める上でも必要なことです。...