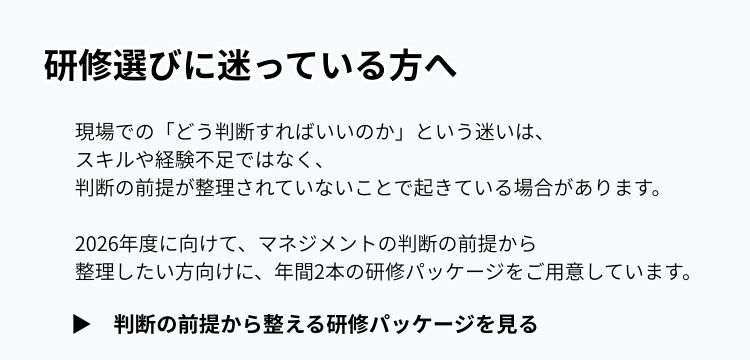【統合失調症】仕事内容の選び方と職場における環境・人間関係
統合失調症は、かつて精神分裂病と呼ばれていたこともあり、「なんとなく危ない病気」という間違った認識が広がってしまったこともあり、「自分たちとは違う、普通ではない人たち」といった印象を抱かれることが多くあります。しかし、実際に統合失調症の人に会い、話してみると、自分たちと同じ普通の人だったと驚く方がほとんどです。 統合失調症の人の多くは働きたいと思っています。どのような病歴があるのかは個人差がありますが、多くの人は働くことや誰かに必要とされることが、誰にとっても大きな生きがいにつながっています。...