その欠勤は本当に“突然”だったのか?
ある朝、メールが届きました。
「体調不良のため、本日はお休みさせていただきます。」
昨日まで元気そうに見えていた社員。職場では特に大きなトラブルもなく、むしろ前向きに仕事に取り組んでいた印象でした。
──なぜ、急に?
──何かあったのか?
──また繰り返されるのでは?
精神障害のある社員と関わるなかで、こうした「突然の欠勤」に戸惑いを感じた経験がある方は少なくないと思います。予定された休みでもなく、理由も明確でない。引き継ぎがないまま、今日の業務に穴が空いてしまう──。
そんなとき、私たちはつい「本人にもっとちゃんと伝えてほしい」と思ったり、「信頼して任せて大丈夫だろうか」と不安になったりします。でも、少し立ち止まって考えてみてほしいことがあります。
その欠勤は、本当に“突然”だったのでしょうか?
実は、本人の中では少しずつ積み重なっていた小さな不調や不安が限界を迎え、表に出ただけかもしれません。
今回は、精神障害のある社員に起きやすい「不調の見え方」と「支援の視点」を整理し、どうすれば“急に”見える出来事の背景に、私たちが早めに気づけるのかを考えていきます。
YouTube
Podcast
精神障害と“見えにくい予兆”の特徴
精神障害のある社員の「不調」は、多くの場合、見た目には分かりにくいものです。本人の中では確かに“しんどさ”が積み重なっていても、それが言葉や態度に表れていない──あるいは、表現しないようにしている──そんなことがよくあります。
その理由には、大きく3つの背景があります。
自覚しづらい
精神疾患のある人の中には、「自分の疲労や不調に気づきにくい」「限界が来てから気づく」という特徴を持つ人もいます。これは“我慢している”というより、脳の働きとして“感覚の鈍さ”があることもあります。
表現しづらい
「体調が悪い」と伝えようと思っても、上手く言葉にできない、もしくは「迷惑をかけるのでは」と遠慮してしまうこともあります。とくに“まじめで責任感のある人”ほど、不調を伝えること=怠けていると思われるのではと恐れる傾向があります。
周囲の期待に応えようとする
職場で「ちゃんとしなきゃ」「普通に働かなきゃ」と無理を重ね、「平気そうに振る舞っていたけれど、実はギリギリだった」というケースも少なくありません。 “普通に見えていた”のは、本人が努力してそう振る舞っていただけなのです。
このように、精神障害のある人の「急な欠勤」は、実際には“突然”ではなく、“積み重ねた小さな不調”が限界を超えて現れた結果だと言えます。だからこそ、職場の仲間は、「何があったのか?」と結果を問うのではなく、「何かサインはあったかもしれない」とプロセスに目を向ける視点が大切になります。
よくある“見えないサイン”とは、何か?
精神障害のある社員が不調に向かっているとき、はっきりと「具合が悪い」とは言わないことが多いものです。だからこそ、周囲は「急に休んだ」と感じてしまいます。
ですが実際には、その前に“小さな変化”=“見えないサイン”が現れていることが少なくありません。
いつもと違う“ちょっとしたズレ”は、こんなところからわかります。
・挨拶がそっけない、声に張りがない
・作業ペースが乱れている(速くなる or 遅くなる)
・休憩に入るタイミングが変わる
・表情がこわばっている/視線が合わない
・「大丈夫です」と繰り返すが、目が泳いでいる
こうした変化は、「よく見ていれば気づけたかもしれないけど、見逃してしまいがち」なものばかりです。でも、それらは“心と体のバランスが崩れかけている”予兆でもあります。
精神的な不調は、ときに身体のサインとして表れることもあります。
身体症状として主に表れるサインは、次のようなものがあります。
・頭痛、腹痛、吐き気
・異常な眠気や、逆に眠れていない様子
・食欲の低下、急な体重の変化
これらは「風邪かな?」と思ってしまうこともありますが、実はストレスや不安による自律神経の乱れが原因である場合も少なくありません。
このサインは、いつも見えるものばかりではありません。「何も言わない」というサインもあります。これは、「何も言わない」「いつも通りを装っている」ことがあるということです。
精神障害のある社員は、「話すこと自体がエネルギーを使う」というケースもあります。そのため、「何も言ってこないから大丈夫」ではなく、「言えていないだけかもしれない」という視点を持つことが大切です。
職場で一緒に働いている人が、「あれ? いつもと違うな」と気づいたときには、責めず、踏み込みすぎず、“寄り添う声かけ”ができるかどうかがキモとなります。この一言が、休む前にSOSを出せる関係性を育てることがあります。
担当者にできる“予兆への対応”
では、「見えないサイン」に気づいたとき、職場で一緒に働く仲間や担当者はどのように対応すればよいのでしょうか?大切なのは、“どう声をかけるか”より前に、“どう受けとめるか”の姿勢です。
「何かあった?」より「最近どう?」
不調の兆しに気づいたとき、「何かあったの?」と直接聞きたくなるかもしれません。しかし、それがかえって本人に“詰問”のように響くこともあります。
おすすめは、「最近、疲れてない?」「少し調子落ちてるように見えたけど、大丈夫そう?」といった、“感想”ベースのフラットな声かけです。本人が話せないときは、話すときは言いたくなったらでOKなこと、無理をしなくてもいいことを伝えると、安心して話せる“余白”を残せます。
不調の判断を“本人任せ”にしない
精神障害のある人は、「頑張らなきゃ」「今日は大丈夫だと思いたい」と、自分の調子に無理にフタをしてしまうことがあります。だからこそ、調子を“言葉にする仕組み”を用意しておくことが効果的です。
たとえば、次のようなことができます。
・出勤時に記入する3段階の体調チェックカード
→ 「元気」「少ししんどい」「かなりつらい」の3つから選んで提出
・“今の気分”を書くだけのミニ日報
・面談や1on1で「業務よりも体調のことを先に話す」習慣をつくる
こうした取り組みによって、「不調を申告すること」へのハードルが下がり、結果として欠勤や突発的な休みを“予防的に”支えることができるようになります。
職場に「理解しようとしてくれる人」がいる安心
最も大切なのは、「話せる場所がある」「わかってくれる人がいる」という心理的安全です。不調そのものをゼロにすることはできなくても、“話せる関係性”があることで、その前に調整したり、休んだあとも戻ってきやすくなります。
あなたがかけた一言が、本人にとって「無理しなくていいんだ」と思えるきっかけになるかもしれません。
視点の転換:「休まないこと」ではなく「安心して相談できること」
企業側としては当然、「急に休まれるのは困る」「安定して出勤してもらいたい」という思いもあるでしょう。ただし、その思いが強すぎると、知らず知らずのうちに職場の空気が「体調が悪くても我慢して来るしかない場所」になってしまうことがあります。
結果として、“限界を超えるまで誰にも言えない”→“ある日突然、来られなくなる”という悪循環が起きやすくなってしまいます。
精神障害のある社員の就労において、「まったく休まない」ことを目標にしてしまうのは、実はとても危険です。人には調子の波があり、特に精神の人にとっては「自分のタイミングで立て直せること」が、働き続けるためのカギになります。
だからこそ、「無理にでも来ること」よりも、「無理なときに“相談できる”こと」のほうが、よほど価値があるのです。
“相談しやすい場”を支える3つの要素
1.申告しても責められない雰囲気
→「またか」「困るよ」ではなく、「伝えてくれてありがとう」が信頼を築きます。
2.選択肢がある安心感
→「今日は無理せず作業を軽くしようか」「30分遅れての出勤でも大丈夫だよ」といった柔軟な対応が、本人の不安を軽減します。
3.戻ってこられる“居場所”がある
→ 休んだあと、「おかえり」の一言があるだけで、戻りづらさは和らぎます。
不調や欠勤そのものをゼロにすることは、現実的ではありません。けれど、「今の自分の状態に気づき、調整しながら働ける力」を育てていくことはできます。
そのために必要なのは、“支える人がいる”という安心の土台です。日々のちょっとした気づき、声かけ、関わり方が、その土台になります。
急な欠勤に戸惑う前に、“前兆に気づける関係づくり”を
精神障害のある社員の「突然の欠勤」。それは、本人のわがままでも、サポートする側の失敗でもありません。“見えないサイン”に気づけず、言葉にならないまま積み重なった不調が、表に出てきただけのことが多くあります。
だからこそ、必要なのは「なんで急に?」と責めることではなく、「もしかすると、あのとき何かサインがあったかもしれない」「次は、もう少し早く気づけるかもしれない」と、視点を未来に向けることです。
誰にでも調子の波があります。特に精神障害の人にとって、調子の上がり下がりを前提にしながら働ける環境は、長く働く力を支えます。そのために必要なのは、「気づける関係」と「話せる場」を組織の文化として根づかせることです。
仕組みや制度も大切ですが、それ以上に、“一緒に働く人”のまなざしや姿勢こそが、最大の支援になります。
・朝のちょっとした体調確認
・1on1で「仕事以外の話」もしてみる
・「何かあれば言ってね」ではなく「最近どう?」とこちらから聞いてみる
そんな小さな一歩から、“休む前に相談できる職場”づくりが始まります。
もっと支援力を高めたい方へ
「もっと早く気づけるようになりたい」
「支援のしかたに自信がない」
「現場にあった対応方法を学びたい」
そう感じた方に向けて、障害者雇用ドットコムでは、現場支援者のためのオンライン講座や実践シートの提供を行っています。「気づける力」と「支えられる関係」を育てるために、ぜひご活用ください。

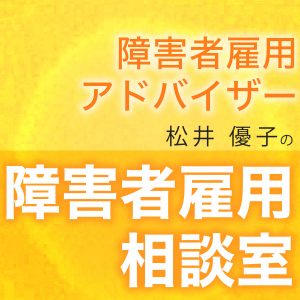









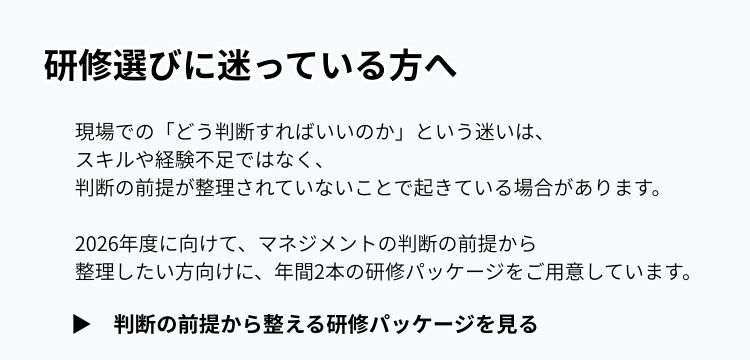















0コメント