障害者雇用は、法的義務の強化や社会的責任の認識が高まる中で、着実に進展しています。しかし、その一方で、採用された障害者が「いるだけ」の存在となり、実際の業務に十分に関与できていないケースも少なくありません。
こうした状況は、障害者本人にとっても企業にとっても課題であり、効果的な雇用の実現を妨げてしまいます。今回は障害者雇用における「いるだけ」状態が生じる原因を探り、その解決策を考察しました。
障害者雇用の「いるだけ」状態とは
日本における障害者雇用は、法的な義務や社会的な責任の意識の高まりとともに、年々増加してきました。多くの企業が、法定雇用率を満たすため、あるいは社会貢献の一環として障害者を採用し、職場に受け入れる努力を続けています。
しかし、実際のところ、採用された障害者が「いるだけ」の状態にとどまってしまうケースも少なくありません。これは、障害者が実際の業務に十分に関与しておらず、組織の一員としての役割を果たしていない状況を指します。
障害者雇用において、「いるだけ」状態とは、採用された障害者が業務に十分に関与せず、組織内での役割が曖昧であるために、実質的な労働力として評価されない状況を指します。
このような状態では、障害者は特定の職務を与えられず、日常的な業務に積極的に参加できないため、組織に対する貢献度が低くなりがちです。その結果、障害者自身も達成感ややりがいを感じられず、企業側も期待される成果を得られないという悪循環が生じることがあります。
なぜ、組織内に「いるだけ」状態ができてしまう5つの原因
障害者が「いるだけ」状態を引き起こしてしまう背景には、いくつかの原因があります。
障害者雇用を「数合わせ」や「形式的な義務」としてしか考えていない
障害者雇用は、確かに障害者雇用促進法で定められていることではありますが、組織にとって組織力をあげたり、さまざまな視点からの人材活用を考えるなどメリットになることがあります。しかし、それらのことが考慮されていないと、障害者雇用を単に「障害者を雇用をすること」としか見なせなくなります。
その結果、「数合わせ」や「形式的な義務」として行われることになります。このような取り組み方をしていると、十分な準備や体制が整っていないために、まさに「いるだけ」の状態を引き起こします。また、企業側も障害者自身もフラストレーションを抱えることになり、結果的に早期離職になってしまいます。
組織に必要な業務設計ができていない
障害者雇用のガイドブックなどには、「障害者の能力や特性に適した職務の設計」を推奨されていることがありますが、障害者雇用の業務設計でまず考えなければならないのは、「障害に合わせた」ではなく、「組織に必要な」または「組織に合わせた」業務です。
障害特性などを考慮して業務を考えても、そもそも業務自体が組織にとってニーズがない業務であれば、その業務はすぐに淘汰されてしまいます。これまで障害者雇用では、事務サポート業務などが切り出されることが多くありました。他の企業がしているからと他の企業で行っている業務を同じように取り組んでも、それらの業務が本当に組織にとって必要でないのであれば、結果的に「いるだけ」の状態を引き起こす原因となります。
以前は、働く障害者の数が限られていたり、組織にいろいろな面で余裕があったりしたので、場合によっては「障害者の特性や能力に合わせた職務設計」が有効なこともありました。しかし、今は働く障害者の種別や能力的なものを見ても多種多様な人材が増えてきていることや、業務に活躍できる人材を求める企業が増えてきていることから、組織に必要な業務設計をすることが不可欠となっています。
業務内容に合わせた人材を採用していない
履歴書や職務経歴書の内容に特に問題は見られず、面接での受け答えも良好であったため採用に踏み切ったものの、実務面での業務がほとんどできず、実際には職場に定着せず、短期間で退職してしまったという経験を持つ企業は少なくありません。
一般的に採用では、求職者の業務経験や知識、スキルに重点を置きがちですが、障害者雇用の長期的かつ安定した雇用を目指すには、業務内容の適性のある人材を採用することが必要です。最近では、ITや専門的な職種での採用もみられるようになりましたが、これらの職種は採用してから育成することはしていません。新卒や未経験者採用であったとしても、少なくともその業務に適した「適性」があるかどうかを見ています。
障害者採用では、そもそも人材の能力や特性として得意なことと苦手なことがわかりやすいケースが多いものです。その業務に求められる適性にあっていない人を育成するのは、教える側も教えられる側もストレスを感じることが少なくありません。
ある企業では実習したところ適性がないと判断した人がいましたが、本人がどうしてもチャレンジさせてほしいと希望したため、トライアル雇用で受け入れることにしました。しかし、実際にはやはり難しかったようです。業務に合わない採用は、障害当事者本人も辛いだけでなく、業務を教える社員のモチベーションを下げ、ストレスを感じさせてしまいます。
このような状態が続くと、割り当てた業務をこなせないので、簡単な業務を考え出さなければならず、結果的に「いるだけ」状態をつくってしまうことになります。また、現場では、次からの受け入れに協力したくないという状況を作ってしまいかねないので、注意が必要です。
サポート体制が構築できていない
障害者が職場で適切に働くためには、企業内でのサポート体制が大切です。障害者雇用で失敗していない企業のほとんどは、業務指導の担当者を決めています。仕事に関して質問や相談のできる担当者を決めておくことにより、当事者の仕事の悩みや体調などを把握しやすくなるほか、仕事のフィードバックをしやすくなります。
担当者を特に決めないで「誰に質問してもいい」と言われる企業もありますが、慣れない環境で質問する人を決めるのは「誰に聞けばよいのか?」と当事者にとって不安に感じさせたり、それを考えることが負担になることがあります。
また、いろいろな人からの説明や指示を受けたりすると、微妙にやり方や説明の表現が個人個人によって違うこともあり、それが原因でることで混乱することもあります。役職者などで席を頻繁に外す人を担当者にするよりも、同じ業務をしていたり、近くに座っている人の方が質問しやすいということもあります。
一緒に働く社員の理解不足
障害者雇用がうまく機能している企業では、障害に対する基本的な研修や理解を進めるための対応が取られています。上司や一緒に働く同僚が障害に対する基本的な理解やその対応策を知らないと「障害への配慮をしすぎてしまう」という状況を引き起こすこともあります。
これは「業務内容に合わせた人材を採用する」こととも関連しますが、どれくらいの業務ができるのかを確認することや、業務に求められていることを明確にしないで採用してしまうと「◯◯障害だから、疲れやすいだろう。」とか「後で、配慮されていないと言われても困る。」などと考えてしまい、業務に直接関係のないことに時間を割かれてしまいがちです。
また、一緒に働く社員への理解は、障害当事者だけでなく、障害者と一緒に仕事をする社員が、働く上で不安にならないように、また当事者への接し方や対応に戸惑わないようにするためにも必要なことです。
当事者が求める「合理的配慮」があるならば、その点についても一緒に働く社員に共有しておくとよいでしょう。障害によっては、業務にどのような支障があり、周囲はどのような配慮が必要なのか、見た目だけではわからない場合が少なくありません。当事者がどのような配慮を職場に求めているのか、職場で一緒に働く社員が事前に知らなければ、対応をすることはできません。
なお、障害者社員の特性や困りごとについて、誰に、どの程度の内容を伝えるのか等については、当事者の希望を尊重するようにします。
「いるだけ」状態にしないためにできること
明確な役割と目標設定
障害者雇用を組織の中でどのような位置づけにするのかは、企業の考え方によって異なります。ただ、障害者を人材として活用したいと考えているのであれば、組織としての考え方を明確にし、それに合わせた具体的な目標設定をしていくことが必要です。これは、人事担当者や現場だけで解決できるものではありません。
最近では、人的資本経営の考え方が浸透してきて、障害者雇用を人的資本経営やダイバーシティという観点から考えることが増えてきました。障害者を人材の中でどのように捉えるのかを組織として考えることは、今まで以上に求められています。
職務設計と役割を定義する
障害者雇用を成功させるためには、業務設計がとても重要です。「障害者雇用のために業務を切り出そう」とする企業をみていると、目の前の障害者雇用率だけを考えていることが多くみられます。業務設計を考える際には、会社や組織全体を見た業務を考えることが必要です。
組織全体の最適化をはかることや、社員のためにより働きやすい環境を作ること、社員全員のキャリアアップを目的とすると、組織に必要な分野や業務が見えてきます。
適性のある人材を採用する
障害者人材は、障害による特性があったり、何らかの配慮を必要としています。そのため採用してゼロから育成することを考えるよりも、業務に適性のある人を採用して育成することが大事です。
求める業務には、どんな適性やスキルが必要なのかを明確にしているでしょうか。これが明確になっていないと、感覚的な判断になってしまいます。業務のスピードや時間、正確性などを判断しやすいように定量化しておくと比較しやすくなります。
これを判断する一番良い方法は、企業実習(インターンシップ)です。適切な企業実習を行って採用していると、半年以内の退職や、採用前に考えていたのと違ったということは、ほとんどありません。企業実習をすることで、スキルや特性を実際の業務で確認することができるからです。
企業実習(インターンシップ)は、採用後のミスマッチを防ぎ、適材適所の人材配置が可能となります。また、実際の働きぶりを見てから採用の判断を下すことができるので、採用後に起こりうる問題を予め把握し、対策を講じやすくなります。
まとめ
障害者雇用を進めていく中で、障害者を「いるだけ」状態に陥らないためには、企業が障害者を人材として活用するという意志と環境を整えることが不可欠です。これは、組織としての人材に対する方針を定めて明確な役割と目標設定を行うこと、組織に必要な業務設計と適性のある人材を採用することが不可欠です。
障害者が「いるだけ」状態になってしまうことを解決するには、担当部門や担当者だけでは解決できるものではありません。障害者雇用を「障害者を雇用する」ことだけとして捉えるのではなく、人的資本経営やダイバーシティという観点から考えることが求められています。
障害者雇用を法的義務、達成しなければならないものと見なして取り組むのか、それとも組織全体に貢献する重要なことや人材として考えて取り組むのかによって、組織にもたらす影響は大きく変わってくるでしょう。
参考
企業戦略としての障害者雇用 ボトルネックからみた業務最適化の実践事例







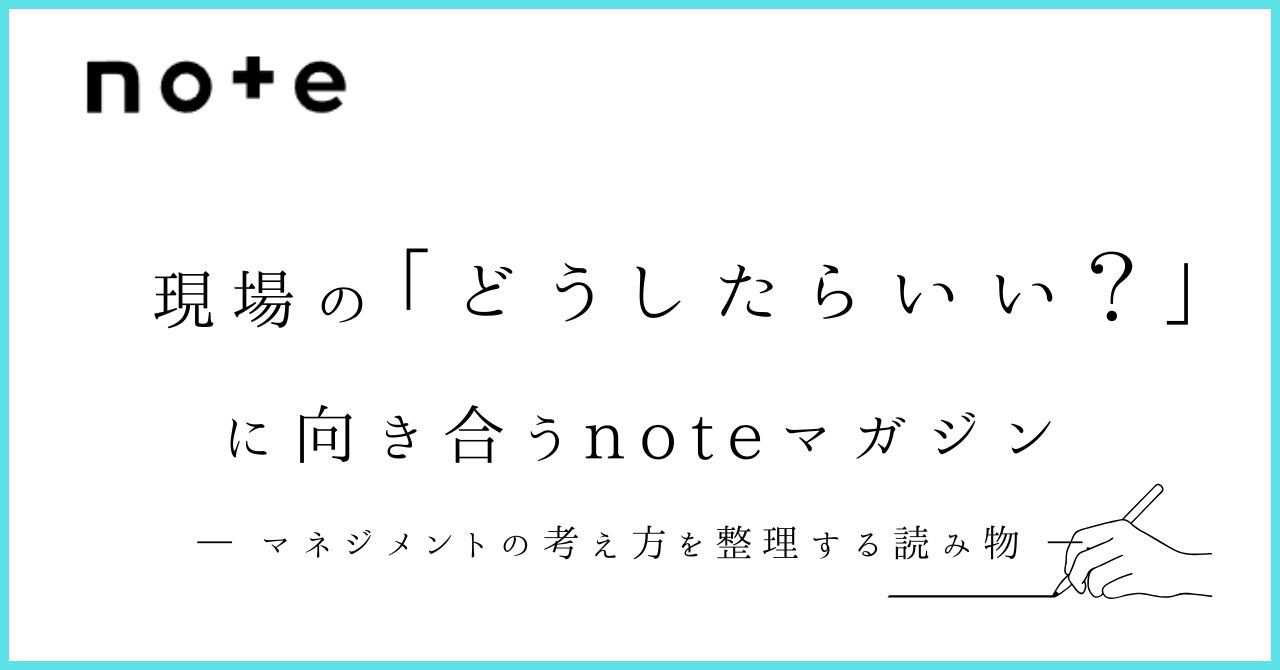


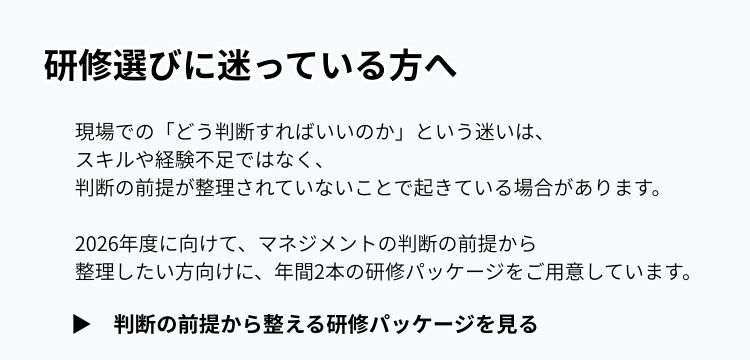


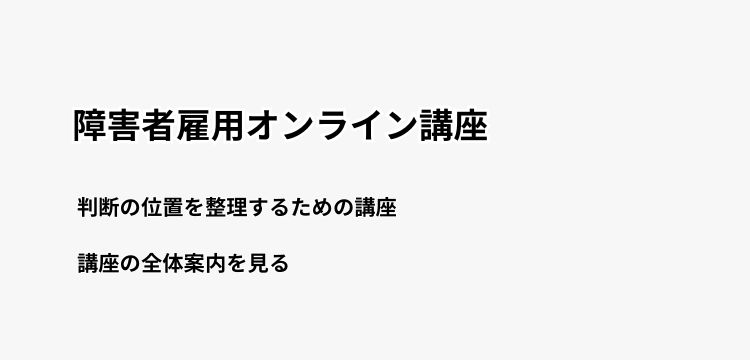












0コメント