「相手のために」と思ってした配慮が、なぜかうまく届かない。そんな経験をしたことがある方も多いのではないでしょうか。
たとえば──
・体調を気遣って仕事量を減らしたのに、本人は「期待されていない」と感じてしまった。
・声をかけると気を悪くされるので、そっとしておいたら「無関心だ」と受け取られた。
現場ではこのような“すれ違い”が少なくありません。
人事や上司は決して悪気があるわけではありません。むしろ、「どうにか力になりたい」「無理をさせたくない」という善意から行動しているケースがほとんどです。それでも、結果的に関係がこじれてしまったり、本人のモチベーションが下がってしまったりすることがあります。
この背景には、“悪意”ではなく、“認知のズレ”があります。相手を思いやる気持ちはあっても、「何をどうすれば相手にとって“届く配慮”になるのか」が共有されていない。つまり、同じ出来事を見ても“見えている構造”が違うのです。
障害の有無に関わらず、職場ではこうした「善意のズレ」が静かに積み重なっていきます。その結果、「配慮しているのに伝わらない」「何が正解かわからない」という声が現場で増えていくのです。
本コラムでは、この“ズレの構造”を見える化し、どうすれば「伝わる・届く」配慮に変えていけるのか、そのヒントを、現場のリアルとマネジメントの視点から考えていきます。
ズレの正体1:配慮が「一方通行」になっている
「相手のためを思ってやったのに、なぜかうまくいかない」 このすれ違いの多くは、配慮が“一方通行”になっていることに原因があります。
たとえば、次のようなケースです。
「無理をさせたくない」と仕事を減らしたが、本人は「期待されていない」と感じてしまった。
「負担をかけたくない」と声をかけるのを控えたら、「放っておかれた」と受け取られた。
「周囲が支えなければ」と細やかにサポートした結果、本人は「自立を認めてもらえていない」と感じた。
どれも“相手のために”という善意から始まっています。しかし、その「ために」が“自分基準の思いやり”にとどまってしまうと、相手には別の意味で伝わってしまうのです。
一方通行の配慮が起きる理由
多くの場合、上司や同僚は「相手の状態を想像して先回りする」ことで安心しようとします。
「これくらいは難しいかもしれない。」
「この言い方は傷つけるかもしれない。」
その想像自体は悪いことではありませんが、そこに本人の声が置き去りになってしまうと、“支援する側の安心”が優先され、“支援される側の実感”が抜け落ちてしまいます。つまり、配慮が「相手のため」ではなく、いつの間にか「自分が安心できるため」にすり替わってしまうのです。
伝わる配慮に変える第一歩
届く配慮は、“確認”と“共有”から始まります。
たとえば、
「このやり方でやりにくくないですか?」
「もしサポートが必要なら、どういう形が助かりますか?」
というように、“本人の感じ方”を確認する対話のプロセスを挟むことです。
一方通行の配慮は、「こうした方がいいだろう」という想定で終わります。届く配慮は、「これで合っていますか?」という確認でつながります。小さな一言の確認が、「守る配慮」から「活かす支援」へと変える鍵になります。
ズレの正体2:“困りごと”を見立てる視点の違い
現場でのすれ違いのもう一つの原因は、「困りごと」をどう見立てるかの視点の違いです。
上司や同僚は、つい「できるか・できないか」という能力の問題として状況を判断しがちです。 一方で、本人は「できるけれど、続けられない」「集中できるときとできないときがある」といった、 環境や条件によって変化する“波”を実感しています。
「できる/できない」の誤解が生むすれ違い
たとえば、ある社員が業務のミスを繰り返したとき。
上司は「理解力が足りない」「指示が通じていない」と捉え、本人は「わかってはいるけれど、情報が多すぎて整理できない」と感じている、このような構図です。
ここでズレているのは、“能力”の話ではなく、“環境との関係”の話です。情報量の多さ、音や人の動きといった刺激、体調の変動、優先順位の不明確さ、それらの外的要因がパフォーマンスに影響していることは少なくありません。
つまり、“できない人”がいるのではなく、“できない条件”がある。この視点の転換が、ズレを解消する第一歩になります。
「能力差」ではなく「条件差」として見る
障害のある社員の支援だけでなく、誰にでも当てはまる原則があります。それは、「能力差」よりも「条件差」に目を向けること。
たとえば、
・明確な手順書があるとスムーズにできる
・周囲の会話が減ると集中できる
・一度に複数の指示があると混乱する
こうした条件を整えるだけで、同じ人が見違えるように力を発揮することがあります。
それにもかかわらず、支援が進まない職場では、「やる気の問題」「性格の問題」といった個人要因のラベルで終わってしまうことが多くみられます。
見立てを変えると、対応が変わる
“困りごと”を「誰の問題」ではなく「何の条件」かと問い直すと、解決策の方向性がガラリと変わります。
・「なぜできないのか」ではなく、「どうすればできるか」
・「どこが弱いのか」ではなく、「何が整えば活かせるか」
こうした視点の変化が、支援を“指導”から“設計”へと進化させます。「困りごと」の見立てが変わると、相手への見方も変わります。
ズレの正体3:“期待値の共有”が不足している
もう一つの見えにくいズレが、「期待値の共有ができていない」ことです。職場でよくあるのが、上司と本人がそれぞれ“いいと思っている方向”が違うのに、お互いが「伝わっているはず」と思い込んでしまうケースです。
たとえば・・・、本人が「できる範囲で頑張ります」と言ったとき、上司は「任せて大丈夫」と受け取る。しかし本人は、「できる範囲=限定的に関わる」という意味で言っている。
上司が「無理しないで」と声をかけたとき、本人は「もう期待されていない」と感じる。一方、上司は「気遣いの言葉をかけたつもり」でいる。
どちらも“悪意”はなく、むしろ互いに気を遣っています。それでも結果として、期待と受け取りのズレが不信感を生むのです。
曖昧な優しさが誤解を生む
人間関係のトラブルの多くは、「伝え方がきつい」よりも「伝えていない」ことに原因があります。特に、“優しさ”が動機になると、相手に配慮して曖昧な表現を選びがちです。しかし、「察してほしい優しさ」は伝わらず、「言葉にしない期待」は、相手を迷わせます。
優しさを本当の意味で相手に届けるためには、
「どこまで任せるのか」
「どこから支援するのか」
を具体的に話し合うことが欠かせません。
「任せる」と「支える」の線引きを明確にする
仕事の任せ方には、“信頼”と“放任”の紙一重の違いがあります。「信じて任せる」は、支援の手を離すことではなく、見守る構えを持つことです。
一方で、支えるとは「手を出す」ことではなく、支えられる環境を整えることです。
たとえば──
・任せるときは、「ここまではあなたに任せたい」と範囲を明確に。
・支えるときは、「何かあったらいつでも相談して」と“戻れる場所”を提示。
このように、期待の輪郭を明確にする対話が、信頼関係の基盤をつくります。
“共有”が関係を育てる
障害者雇用の現場でも、「任せる勇気」「支える設計」が両立している職場ほど、本人の力が発揮され、組織全体の安定度が高い傾向があります。
つまり、“届く配慮”とは、「伝える」よりも「共有する」もの。善意を伝えるだけではなく、一緒に意味づけるプロセスこそが、ズレを埋める鍵になります。
“届く配慮”に変えるための3つのヒント
ここまで見てきたように、“善意の配慮”がうまく届かない背景には、「一方通行」「見立てのズレ」「期待値の共有不足」という構造があります。
では、どうすれば“伝わらない配慮”を“届く支援”に変えられるのでしょうか。
現場で実践できる3つのヒントを紹介します。
1.聞く前に“決めない”
配慮がすれ違う最大の原因は、「きっとこうだろう」と先に決めてしまうことです。多くの上司は、相手を気遣うあまり、相手の声を聞く前に結論を出してしまう傾向があります。
「きっと疲れているだろうから、任せないでおこう」
「指示されるとプレッシャーになるだろう」
しかし、その想定が相手の実感と違えば、 “やさしさ”が“距離”に変わってしまいます。
まずは、相手の感じ方や希望を聞くことから始める。たとえ時間がかかっても、「どう思う?」「どんな方法がやりやすい?」と尋ねることで、相手の自己決定を尊重する関係が生まれます。
2.支援を“共有の作戦”にする
支援とは、“上から与えるもの”ではなく、“一緒に考えるもの”です。現場では、「助ける側」と「助けられる側」という関係が固定化すると、お互いに気を遣いすぎて、本音を言えなくなることがあります。
届く配慮に変えるには、支援を“共同行動”に変える発想が必要です。
たとえば、
「一緒にうまくいく方法を考えましょう」
「このやり方でうまくいくか、試してみませんか?」
といった言葉を使うだけで、関係性のトーンが変わります。“手を差し伸べる”ではなく、“同じ方向を見る”関係にする。この姿勢が、配慮を相互理解と協働のプロセスへと進化させます。
3.言葉より“確認のプロセス”を増やす
「伝えたつもり」「わかってくれたはず」。
この“つもり”の積み重ねが、ズレを広げる最大の要因です。
届く配慮に変えるには、一度きりの伝達ではなく、確認を繰り返すプロセスを意識することが大切です。
「この伝え方で合っていますか?」
「今の説明でわかりづらいところはありませんか?」
「この方法でやってみて、どうでしたか?」
確認の言葉は、単なる“チェック”ではなく、対話の継続の合図です。相手を尊重する姿勢が伝わり、信頼が育ちます。
届く配慮とは、「相手を思う」ことではなく、「相手と確認し続ける」こと。それは、“やさしさの瞬間”ではなく、“関係を育てる習慣”です。小さな対話の積み重ねが、現場の安心をつくり、その安心が、社員一人ひとりの力を引き出していきます。
まとめ:配慮の目的は「守ること」ではなく「力を活かすこと」
「配慮=守ること」と考えられがちですが、本来の目的は相手の力を活かすことにあります。
相手を思う気持ちは大切です。ただし、思いやりを“行動”や“仕組み”に変えなければ届きません。
届く配慮とは、相手の声を聞き、一緒に方法を考え、確認を重ねながら進めること。
このプロセスが、信頼を生み、チームの力を引き出します。障害者雇用の現場で磨かれる「届く配慮」の力は、実は組織全体のマネジメント力を高める土台にもなります。守るための配慮から、活かすための配慮へ。
やさしさを言葉と仕組みに変えられる職場が、多様な人の力を最大限に発揮できる組織をつくります。
関連コラム
・ なぜ、精神障害のある人に「頑張って」と言ってはいけないのか(NewsPicks「障害者雇用~多様性を力に変える組織づくりに~」)
→ “励まし”のつもりがプレッシャーに変わるとき。
相手の状態を尊重しながら支えるコミュニケーションのヒント。
・「合理的配慮」がうまくいかない本当の理由─“やさしさ”を仕組みに変える視点 (NewsPicks「障害者雇用~多様性を力に変える組織づくりに~」)
→ 配慮の個別対応から、再現性あるマネジメントへ。
・「精神」と「知的」では伝え方が違う─“教え方”がうまくいかない理由とは?
→ 障害特性に合わせた伝え方・関わり方のヒントを紹介。
関連サービス・プログラム
▼ 現場リーダー・上司向け研修
・1on1/合理的配慮/ハラスメントの“グレーゾーン”対応
・「伝える」から「伝わる」へ。行動変容を生むリーダー育成。
研修内容を見る
▼ コンサルティング・個別支援
・法定雇用率達成から「雇用力」強化へ
・採用~定着~マネジメントを統合的に支援
詳細・お問い合わせはこちら
▼ note
「現場の善意を成果につなげる人事の視点」シリーズ
障害者雇用・合理的配慮・マネジメント力向上に関する最新の知見を配信中。










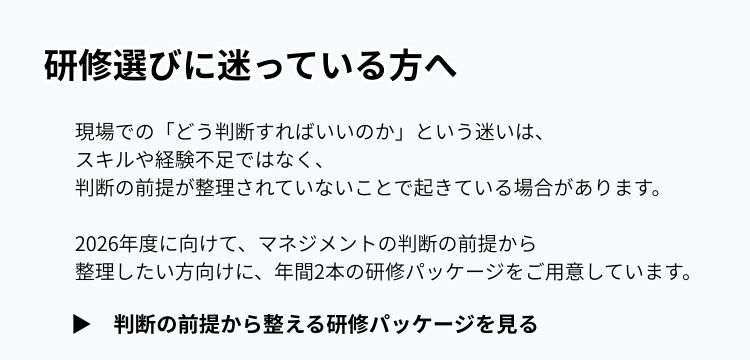















0コメント