障害について尋ねることは、相手を理解するための重要なステップとなります。特に障害者雇用の場面では、個々のニーズに応じた合理的配慮を提供することが求められています。
一方で、多くの人が「障害について尋ねてもいいのか」とためらう場面があるのも事実です。「傷つけてしまうのではないか」という不安や、「適切な言葉や聞き方が分からない」といった戸惑いを抱えることは少なくありません。
今回は、障害について尋ねることに対する心理的なハードルを少しでも下げ、相手を尊重しながら効果的にコミュニケーションを取る方法について考えていきます。
なぜ障害について聞くことをためらうのか?
障害について尋ねることは、相手を理解するための重要なステップです。単に相手の状態を知るだけではなく、相手がどのようなサポートを必要としているのかを明確にすることができるからです。これは、相互理解を深め、偏見を減らすための有効な手段となります。
質問することは、相手を理解するのに役立つことを知っていながら、私たちが障害について尋ねることに対する最も大きなハードルの一つとなっているのは、心理的な抵抗、過去の失敗や不安、社会的なタブー視があります。
心理的な抵抗としては、「相手を傷つけてしまうのではないか」と考えてしまうことがあります。相手の感情を尊重しようとする気持ちが強いほど、「聞くこと自体が失礼になるのではないか」「無神経だと思われないだろうか」といった不安が先立ち、結果として質問を控えてしまうのです。このような恐れは、障害に関する理解が深まることを妨げる要因となるだけでなく、必要な対話の機会を逃す原因にもなります。
過去の失敗や不安という点については、過去の経験で相手を不快にさせてしまった経験がある場合、その記憶がトラウマとなり、再び同じ失敗を繰り返すのではないかという不安を抱くことがあります。また、障害に関連する正しい言葉選びや聞き方について十分に学んだ経験がない場合、「どのように聞けば良いのか分からない」という戸惑いが対話への意欲を阻害することもあります。
障害に関する話題がタブー視されがちな社会的な風潮も、質問をためらう要因の一つです。「障害について触れるべきではない」という暗黙のルールが存在するように感じられる社会環境の中では、障害に関する話題を切り出すこと自体が勇気を要する行動となります。このような風潮が、個々人の間にある溝を広げ、相互理解の妨げになることも少なくありません。
相手を傷つけないための基本的な心得
障害について質問する際には、相手の立場や感情に配慮しながらコミュニケーションを取ることが何よりも重要です。相手を傷つけることなく理解を深めるための基本的な心得について見ていきます。
・リスペクトする
まず第一に、相手の価値観や感情を尊重する姿勢が必要です。どのような質問であっても、軽率な態度や興味本位の接し方は相手を不快にさせる可能性があります。「知るための対話」ではなく「相手の気持ちを尊重する対話」を心がけることで、信頼関係を築く土台が作ることができます。
・意図を明確にする
質問をする際には、その意図を率直に相手に伝えることが大切です。「理解を深めたい」「最適な合理的配慮を提供したい」といった前向きな理由を相手に伝えることで、あなたの意図が純粋であることが相手に伝わり、安心感を与えることができます。意図を明確にすることは、特に企業における合理的配慮を進める場面で重要です。
・無理に聞かない
相手が話したくないと感じる場合には、その気持ちを尊重する姿勢を示します。たとえ知りたい情報が得られなくても、無理に聞き出すのではなく、相手が「話してもいい」と感じる環境を整えることが大切です。無理に聞こうとすると、相手との信頼関係を損なうリスクが高まります。
障害について聞くことが必要な理由
相手に配慮しながらも障害について聞くことは、企業で障害者雇用を進めるうえでとても重要なことです。企業では、障害者に合理的配慮を示すことが求められています。合理的配慮の考え方としては、障害者から事業主である企業に対して、職場で示してほしい配慮を申し出て、企業側が検討することになっています。そのため企業が障害者の必要な合理的配慮について知る機会となるのは、採用面接するときに把握できることが多いです。
しかし、障害者本人に合理的配慮についての知識があり、企業へ伝える準備ができている場合ばかりではありません。また、採用に支障があるのではないかと考えて、採用前に必要な配慮を自ら申し出ないケースもあります。そんな場合も想定して、企業から面接の際に聞いておく必要があります。
企業にとっては、求められる合理的配慮がどこまで応えられるのかを検討したり、「過重な負担」となるような場合には対応が難しい理由を伝える必要もあります。また、合理的配慮の実施には、それを遂行できるように環境を整えることも必要となります。殆どの場合は、一緒に働く上司や同僚が障害の特性や配慮事項を知らないと、求める配慮を示すことが難しいからです。そのため障害当事者の具体的なニーズを正確に知ることが必要ですし、それを把握することで適切なサポートや職場環境の整備が可能となります。
私が直接的、間接的に関わってきた中では、障害についての質問を聞く理由を明確に示したうえで質問したことにより、トラブルになったことは今までありません。真摯に話を聞き、相手を理解しようとする姿勢があれば、問題が起こることはないでしょう。それよりも障害者雇用においては、適切な対話を通じて、信頼関係を築くきっかけになることもあります。
また、企業がおさえておきたい点として、最近、合理的配慮に関する訴訟がよく聞かれます。障害者雇用で「配慮を示すこと」は大事ですが、この配慮だけを過大に取り上げられるケースがよく見られます。障害者雇用は「雇用」であり、求められる業務を行う上で合理的配慮を示すことはあっても、「配慮」を示すために行っているわけではありません。この点を企業側でもしっかり認識し、採用段階で求める合理的配慮とともに、仕事に対する考え方や姿勢を聞いておくことは、企業のリスク管理にも役立ちます。
後から、トラブルになるケースの多くは、事前に聞いておくべき質問を遠慮して聞いていないことが見られています。確かにセンシティブな内容で聞くことをためらってしまいたくなる気持ちもわかりますが、障害者も企業もお互いが働きやすい職場にするためには、よくコミュニケーションを取ることが必要です。よかれと思っての行動も、一方的な配慮ではかえって逆効果になることもありますので、話し合いながら、本人の意向をよく汲み取って進めてください。
まとめ
障害について尋ねることは、相手を理解し、職場環境や人間関係をより良いものにするために欠かせない行為です。しかし、心理的な抵抗や社会的なタブー視によって、質問をためらうことも少なくありません。本コラムでは、そのような不安を軽減し、相手を傷つけることなく、適切にコミュニケーションを取るためのポイントを考えてきました。
障害者雇用の現場では、合理的配慮を示すために相手の具体的なニーズを正確に知ることが必要です。そのためには、適切な質問を行うことで、相手の状況を理解することがどうしても必要になります。
大切なポイントは、質問の目的や意図を明確に伝え、相手の気持ちを尊重しながらコミュニケーションを進めることです。質問を通じて得た情報をもとに、双方にとってより良い働き方を共に考える姿勢が、信頼関係を深め、長期的な成功を生むものにつながります。










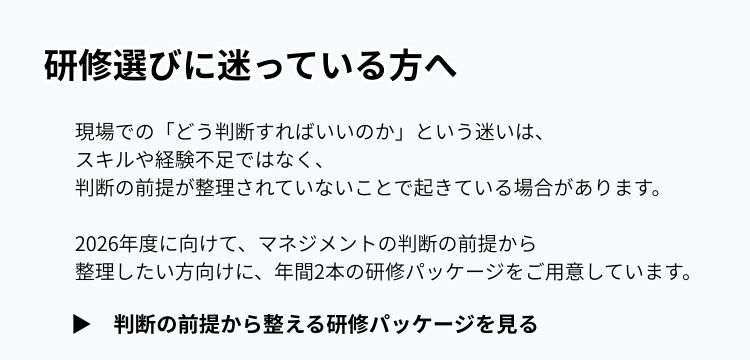















0コメント