「障害者雇用」と聞くと、多くの人は「企業が法律に従って雇うもの」と考えがちです。確かに、日本では障害者雇用促進法により、一定規模以上の企業には障害者を雇用する義務があります。しかし、障害者雇用は単なる法的義務にとどまらず、組織にとって企業の競争力を高めることにつながることもあります。
近年、社会全体でダイバーシティ&インクルージョン(D&I)が強く求められるようになり、企業においても「多様な人材を活かすこと」が成長戦略の一環となっています。その中で、障害者雇用は特に注目されるテーマの一つです。多様な視点を持つ人々が共に働くことで、新しい発想が生まれ、組織の柔軟性や創造性が向上するからです。
とはいえ、直接関わっていないと、障害者雇用ってどういうものなのか?という方もいると思います。今回は、障害者雇用の基礎知識やそのメリット、現場でよくある誤解について紹介していきます。
動画で見る
Podcastできく
今さら聞けない障害者雇用の基礎知識
障害者雇用について「法律で決められているから必要」と聞いたことがあっても、具体的なルールや対象範囲を詳しく知らないという方もいます。ここでは、障害者雇用の基本を整理し、企業に求められる義務やメリットについて解説します。
法律面:障害者雇用促進法と法定雇用率とは?
日本では「障害者雇用促進法」に基づき、企業に対して障害者の雇用を促すためのルールが定められています。その中心となるのが「法定雇用率」です。
企業は一定割合の障害者を雇用することが義務付けられており、これを法定雇用率といいます。2024年4月からは以下のように改定されています。
・民間企業:2.5%(従業員40人以上の企業が対象)
・国・地方公共団体:2.8%
・都道府県等の教育委員会:2.7%
企業の従業員数が増えるにつれて、雇用すべき障害者の人数も変わります。例えば、200人の従業員がいる企業なら、2.5%にあたる5人以上の障害者を雇用する必要があります。
対象者:どんな人が「障害者雇用」の対象になるのか?
障害者雇用の対象となるのは、以下の3つの障害者手帳のある人です。
・身体障害者(視覚・聴覚障害、四肢の欠損、心臓や腎臓の機能障害など)
・知的障害者(知的発達に遅れがある方)
・精神障害者(うつ病、統合失調症、発達障害などを含む)
発達障害(ADHD・自閉症スペクトラムなど)も精神障害の一部として、障害者雇用の対象とされており、雇用人数は増えています。これらの障害者手帳(身体・療育・精神)を取得している場合、企業の法定雇用率の対象となります。
企業の義務:雇用率未達成企業に求められること
法定雇用率を達成できていない企業には、以下のような対応が求められます。
・「障害者雇用納付金」の支払い(対象:常時100人以上の従業員がいる企業)
未達成の企業は、不足人数1人あたり月額50,000円の納付が必要。
・行政指導の対象となる可能性
労働局、厚生労働省から指導を受け、改善計画の提出を求められることもある。
・社会的なイメージや採用活動への影響
企業の社会的責任(CSR)を問われ、求職者や投資家からの評価が下がる可能性がある。実際に株主からの訴訟問題が1999 年におこっている。JAL 訴訟問題では、1999 年12月17 日、JAL の一部の株主が「同社の経営者が障害者の雇用を積極的に行わずに多額の障害者雇用納付金を支払い、同社に納付金相当の損害を与えてきた」としてJAL の経営者を相手に株主代表訴訟が行われた。結果としては、被告が譲歩するという形で和解が成立。
法定雇用率を達成している企業のメリット
一方で、法定雇用率を達成している企業には、以下のようなメリットがあります。
・「障害者雇用調整金」や「報奨金」の受給
法定雇用率を超えて雇用している企業には、企業規模に応じ「障害者雇用調整金」や「報奨金」が支給。
・企業のブランドやイメージ向上
ダイバーシティ推進企業として評価が高まり、投資家や顧客、求職者に好印象を与える。
・助成金・補助金の活用
障害者の雇用や職場環境の整備に対する助成金や、自治体の補助金を受けられる。
企業にとっての障害者雇用のメリット
ここまでは、障害者雇用の基礎知識として、法律や企業の義務として求められること、法律遵守のメリットについて見てきました。ここからは、障害者雇用が組織にもたらすメリットについて見ていきます。
1.業務プロセスの見直しとコスト削減
これは、ある特例子会社さんの事例です。設立当初はコピーやシュレッダーなどの軽作業が中心で、法定雇用率は満たしていたものの、売上や利益への直接的な貢献は低く、「コスト」としての側面が強かったそうです。
しかし、グループ全体でコスト構造の見直しが進んだことを機に、特例子会社も事業部門に貢献できるような業務へとシフトが求められました。そこで社員の特性や得意分野を活かし、より高度な業務を受託することで、戦力化とモチベーション向上を実現しました。
具体的には、次のようなことが実現しました。
・外部委託や派遣に比べて人件費が抑えられる
社外への業務委託や派遣社員雇用のための人件費と比較するとコスト優位性を示すことができました。
・社内リソース活用により、見積・稟議・契約などの事務負担が軽減
社外であれば業務発注時には、見積り取得や社内稟議、契約書のまき直しなどの工数が多々発生します。自社グループ内で行うことにより、ある程度現場判断で柔軟に対応することが可能となり、事務的な負担が軽減しました。
・共通のネットワークやシステムを使うことで業務環境整備が容易
業務を外注していたときには、環境を整えるための工数がかかっていました。しかし、グループ内で同じインフラ、例えば社内のネットワークや共通のシステムを使用することができるため、業務環境整備から始める外部への業務委託よりも環境面を整えやすくなりました。
・業務ノウハウが社内に蓄積され、継続的な改善が可能
外部にアウトソースすると、業務のノウハウが自社に蓄積されず、毎回要件を確認する必要がありました。しかし、グループ内に内製化したことで、そのノウハウを蓄積することができるほか、業務に携わるメンバーのスキルもわかり、適切な業務配置が今まで以上に進みました。
2.障害の有無に関係なく働きやすい職場になる
障害者が職場にいることで、誰にとっても働きやすい職場を作りやすくなります。ある企業では、車いすの社員が電動ドライバーを取ろうとして、腕を前に出したところ、バランスを崩し、車いすから転げ落ちそうになってしまいました。そこで、工具に手元に戻ってくるようなバネをつけたところ、業務の改善につながり、1ヶ月にすると200分の業務短縮に繋がりました。
この他にも、車いすに絡まないようにするためにLANケーブルの巻取り機を設置して、コードに引っかかることを回避したり、在庫が1つになると黄色いタグがでてきて、発注のタイミングが誰にでもわかるなどの工夫がされています。このような誰にとっても業務がしやすい、わかりやすい取り組みが工場内の随所に行われ、働きやすい職場づくりが実現しています。
3.気づきや物事の見方が変化する、視野が広がる
障害者雇用の効果は、単に業務効率やコスト削減といった目に見える成果だけではありません。実は、社員一人ひとりの“気づき”や“物事の見方”に変化が生まれ、組織全体の視野が広がることも、大きな価値のひとつです。障害者雇用に取り組んだことで、今まで知らなかった社会を知れたという声もよく聞かれます。
障害のある社員と共に働くことで、職場のメンバーは今まで意識していなかった“前提”に気づかされることがあります。例えば、情報を教える際に「目で見て分かる」マニュアルなどを重視していたものの、読むことが苦手な人もいることから「音で伝える工夫」をすることで、情報を入手しやすいことに気づくことがあります。
また、毎日行っている業務が実は非効率で、別のやり方のほうが効果的で、全員にとってわかりやすかったり、効率的になったと気づくこともあります。このように、障害社員の視点や行動が、職場に「問い」を投げかけてくれる存在となり、固定観念にとらわれない思考や創造力を刺激することや、今まで「当たり前」が揺さぶられ、思考が深まるということもあります。
現場でよくある誤解とリアルな実態
とはいえ、障害者雇用に関して、企業の現場ではさまざまな誤解が根強く残っています。
「負担が大きいのでは?」「戦力にならないのでは?」「職場の雰囲気が悪くなるのでは?」といった懸念を持つ人も少なくありません。しかし、実際には適切な環境整備やマネジメントによって、こうした問題は十分に解決可能です。
ここでは、よくある誤解とそのリアルな実態について解説します。
誤解1「特別な配慮が必要で負担が大きい?」
【実態】必要な配慮はあるが、適切な環境整備で十分対応可能
「障害のある社員を雇用すると、多くの配慮が必要になり、企業の負担が増えるのでは?」と思われがちですが、事前に準備や環境整備を行うことで、過度な負担が発生するケースは少なくなります。
環境整備のポイントとしては、次のようなことができます。
・車いす利用者のためのスロープ設置や机の高さ調整
・聴覚障害のある社員向けの筆談ツールやチャットツールの活用
・視覚障害のある社員にはスクリーンリーダー(音声読み上げソフト)の導入
これらの工夫は大きなコストをかけなくても可能であり、ICT技術の発展により、多くの支援ツールが低コストまたは無料で利用できるようになっています。また、助成金や補助金を活用することで、企業の経済的負担を軽減することも可能です。
最近は、特にAIを活用したツールも目まぐるしく進んでおり、これらを活用することで、さらに業務が行いやすくなっています。例えば、情報を「視覚」と「音声」の両方で伝える仕組みを整えることで、健常者の社員にとっても業務の効率が向上するケースがあります。
誤解2「仕事の戦力にならない?」
【実態】強みを活かす配置で企業の生産性向上に貢献
「障害者は仕事ができない」「職場で戦力にならない」というのは、大きな誤解です。適性がある人材を適切な配置をすれば、障害のある社員が企業の生産性向上に貢献するケースは数多くあります。
例えば、発達障害のある社員の中には、高い集中力やこだわりの強さ、ルールへの忠実さ、パターン認識力を持つ方がいます。これらの特性は、一定の条件下では非常に高いパフォーマンスを発揮します。
あるIT企業では、発達障害のある社員がデータの整合性チェックや不正ログの検出業務に配置されました。彼は繰り返しパターンの中から違和感を見つける力に優れ、ミスの発見率は他の社員の倍以上を記録します。結果として、品質管理プロセスの精度が向上し、社内でも重要な役割を担うようになりました。
このように、「できないこと」ではなく、「得意なこと」に着目し、環境を整え、適材適所の配置をすることで、職場で活躍する存在となっているケースは少なくありません。大切なのは、“障害があるかどうか”ではなく、“適性のある人材を適切な場所に配属する”という視点です。この視点を持つことが、企業全体の活性化につながります。
誤解3「職場の雰囲気が悪くなる」
【実態】事前の研修や社内の理解促進で円滑なコミュニケーションが可能
「障害のある社員を受け入れると、職場の雰囲気が変わってしまうのでは?」という不安を持つ企業もあります。しかし、適切な研修やコミュニケーションの工夫をすることで、障害者を受け入れる前よりもコミュニケーションが多くなり、職場の雰囲気が良くなったというところは少なくありません。
このようにできている企業の職場の特徴は、障害社員に必要な合理的配慮について、周囲の社員が理解しやすい、協力しやすい状況をつくっているということです。一部の社員だけが知っていても、一緒に関わる社員が理解していないと配慮が示せなかったり、誤解を生むきっかけになることもあります。
例えば、薬の副作用などで、仕事中に眠そうにしている社員を見たときに、薬が変わって副作用の影響で調子が悪いことを理解していればそれを気遣う言葉をかけられるかもしれません。一方、そのような背景や事情がわからないと、仕事中に眠そうにしているなんて、自己管理ができていない、仕事に対する意識が甘いと感じてしまうでしょう。
障害に関してはセンシティブな内容なので、ごく一部の人にしか伝えないことを配慮と思っている方がいますが、時には逆に職場の雰囲気を悪くしてしまう要因になることもあります。もちろん当事者の意見を尊重することも大切ですが、職場の業務内容や環境によっては、周囲の人に理解できる環境を整えることは重要です。
そのためには、 受け入れ前に次のことをしておくとよいでしょう。
・障害のある社員本人との面談(必要な配慮について確認)
・従業員向けの事前研修(障害の理解を深める)
・チーム内の受け入れ準備(役割分担やサポート体制を明確化)
まとめ
障害者雇用というと、「法律で決められているから仕方なく行うもの」と考える方もまだ多くいます。しかし、実際には障害者雇用は、企業にとって大きな可能性と価値をもたらす戦略的な取り組みとすることができます。
法定雇用率を満たすことはもちろん重要ですが、それ以上に注目すべきは、業務の見直しによる効率化やコスト削減、職場全体の働きやすさの向上、そして組織の視野の広がりといった、本質的なメリットです。
また、「障害があるから難しい」「特別な配慮が必要で負担が大きい」といった誤解は、適切な理解と準備によって解消できます。障害者雇用を進めていくときに重要なのは、障害者だけではなく、一緒に働く社員が受け入れやすい体制や職場の雰囲気を作っていくことです。社員の特性に合わせた業務や配置を行うことができるようになると、誰もが活躍できる職場づくりが実現します。

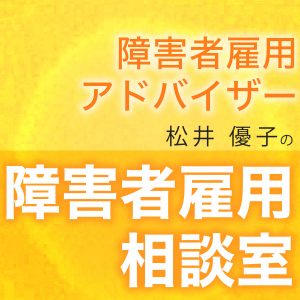









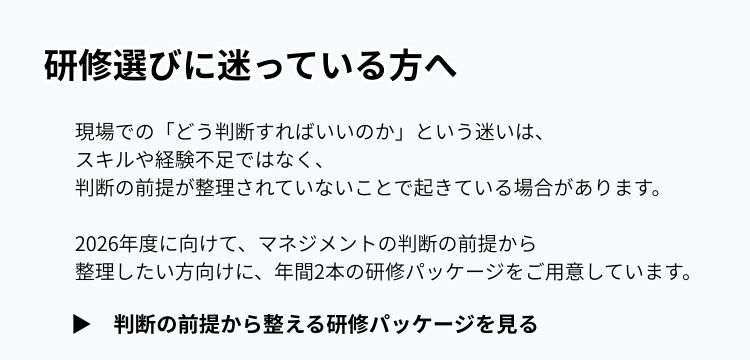















0コメント