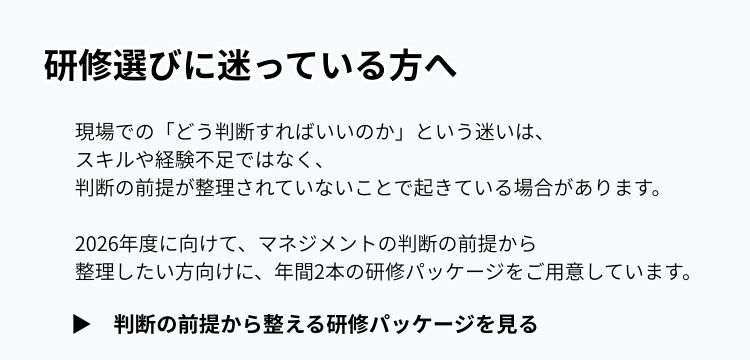社内に障害者がいるかどうかを確認したいときに行う手順とは?
障害者雇用が未達成の場合、もしかしたら社内の中で障害者手帳を持っている社員がいるかもしれない・・・と思うことがあるかもしれません。しかし、障害者手帳の有無について確認することは、個人的なプライバシーに関することで慎重に扱うべきことです。そんなときには、どのように社員に周知することができるのでしょうか。 社内に障害者がいるかどうかを確認したいときの手順や気をつけるべき点について見ていきましょう。 社内で障害者を把握・確認する機会はいつ?...