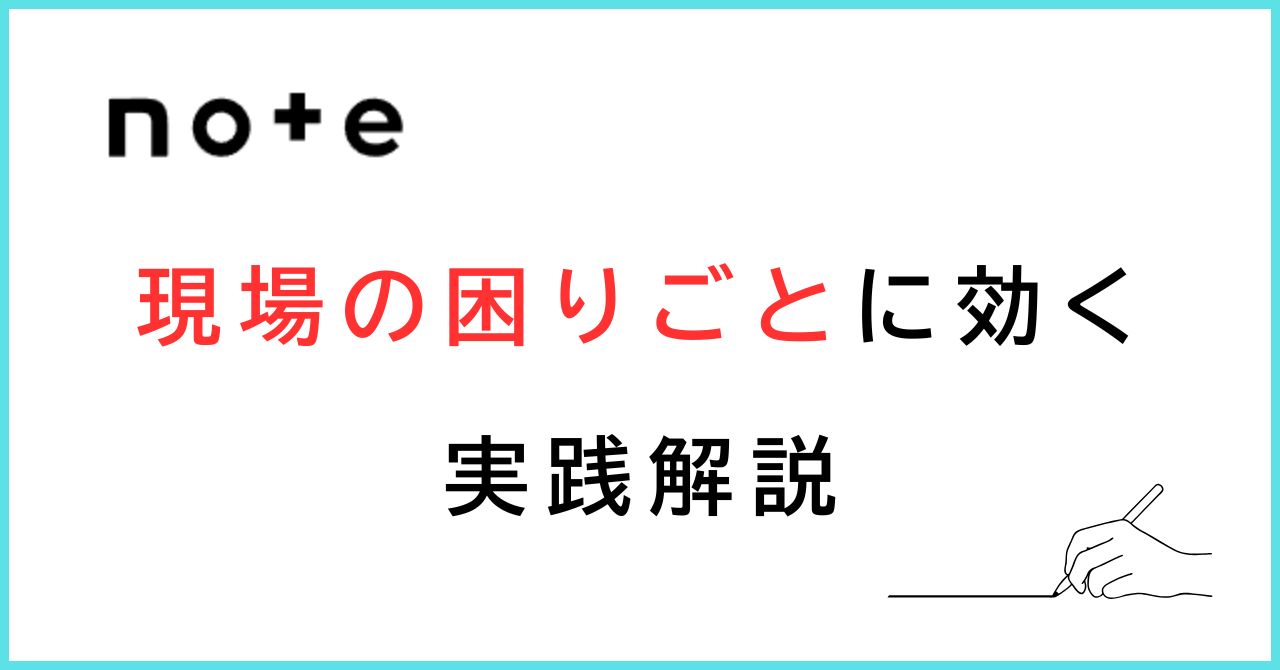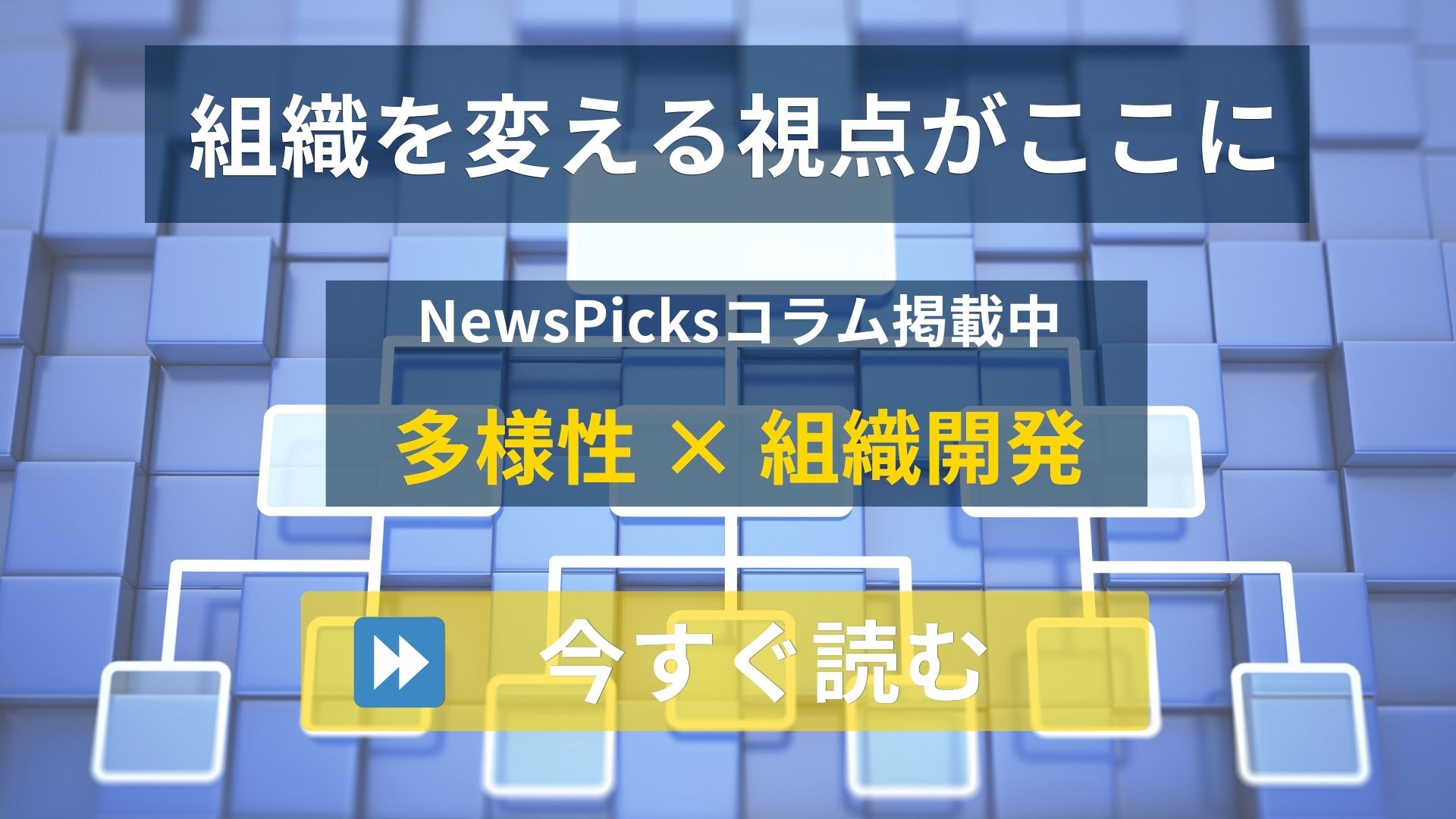精神障害の障害者雇用カウントに関するQ&A~休職、障害者把握~
うつ病やメンタル的な精神障害のある社員を抱える企業は少なくありません。一方、障害者雇用率は、まだ不足している・・・。このような場合、障害者雇用にカウントすることができるのでしょうか。 精神障害をはじめとしたカウントに関するQ&Aに答えました。 休職者を精神障害として障害者雇用率にカウントすることができるか Q:うつ病やメンタル的な疾患のある社員を抱えているものの、障害者雇用率は、まだ不足している。このような場合、障害者雇用率にカウントできないものか・・・と考えていますが、実際にカウントすることはできるのでしょうか。...