「法定雇用率を達成しているかどうか。」
障害者雇用の取り組みを語るとき、まず最初に出てくるのはこの数字です。
もちろん、法定雇用率の達成は社会的責任であり、企業としての最低限の義務です。障害者雇用を担当する人事や経営企画の立場から見ても、数字だけでは見えてこない“成果の実感”があるはずです。しかし、その数字だけを“成果”と見なすと、現場の実態や組織の変化を見落としてしまうことがあります。
実際、雇用率を満たしている企業の中には、
・採用後の定着に苦しんでいる
・現場の負担が増し、サポートが制度依存になっている
・「やることはやった」という安堵感が広がり、取り組みが停滞している
といった声も少なくありません。
一方で、雇用率が一時的に未達であっても、
・上司や同僚の理解が進み、支援の質が向上している
・職場の風通しが良くなり、メンタル不調や離職が減っている
・障害者雇用の経験が、他の人材マネジメントにも活かされている
こうした企業もあります。
つまり、数字が示すのは「結果の一部」でしかなく、組織がどのように変化しているかを捉えることこそが本質的な成果の指標となります。
障害者雇用の取り組みを「雇用率の達成度」だけで判断していないだろうか。その問いかけが、これからの人材戦略を見直す第一歩になります。
本来の“成果”とは何か:数字を超えた3つの視点
障害者雇用の「本当の成果」とは何でしょうか。
それは、障害者を雇用するという法定雇用率という“量的な達成”の先に、組織の質的変化をどう起こしていくか、この視点を持てるかどうかが、今後の企業力を左右します。
数字を超えて成果を見出すための3つの視点には、次のような点があります。
組織文化の変化─「違い」が受け入れられる職場づくり
障害のある社員の受け入れは、単なる雇用ではなく、職場の価値観を問い直す機会ともなります。
たとえば、仕事の進め方やコミュニケーションの多様性に触れることで、社員一人ひとりが「相手に合わせる」だけでなく、「相互に理解しようとする姿勢」を持つことができます。
こうした小さな変化が積み重なることで、
・意見を言いやすい
・困ったときに相談できる
・誰かのつまずきをチームで支える
といった心理的安全性の高い文化が育まれていきます。
それは障害者雇用の枠を超え、組織全体の土台を強くしていくプロセスにもつながります。
マネジメントの成熟─現場リーダーが育つ
障害者雇用の現場では、「伝わるように伝える」「できる環境を整える」など、個別に合わせたマネジメントが求められることが多くあります。
そのためこのプロセスでリーダーや管理職は、自然と
・相手の理解度を見極める観察力
・課題を構造的に整理する分析力
・合意を形成する対話力
を磨いていくことができます。
これらは、障害者雇用に限らず、すべての部下育成や人材マネジメントに通じる普遍的な力です。つまり、障害者雇用は“人を育てるマネジメント力”を高める機会としても機能します。
経営資源としての多様性活用─業務改善と価値創出へ
障害のある社員を受け入れる過程で、多くの企業が業務の可視化・手順の整理・環境整備を進めます。これは単なる「配慮」ではなく、生産性を高める経営活動そのものにつなげることができます。
属人的な仕事を分解してチームで共有することは、
・ムダやミスの削減
・属人化の解消
・プロセスの標準化
につながり、結果として部門全体の生産性向上をもたらします。
さらに、「多様な人が働ける設計」は、育児や介護、外国人雇用、高齢社員の活躍など、他の多様性対応にも転用可能です。実際に障害者雇用を上手にしている企業では、今いる社員が働きやすい環境を整えていた結果、特別なことをしなくても障害者の受け入れが進んでいたという事例もあります。
障害者雇用は、“社会的責任”ではなく、企業の成長を支える経営資源の一つと捉え直すことは、組織全体へのプラスの影響があります。数字の達成だけでは見えない“本当の成果”は、
組織の中に「変化を受け入れ、活かす力」が育っているかどうかにあると言えます。
なぜ“法定対応”では成果が出ないのか
多くの企業が障害者雇用に取り組むきっかけは、「法定雇用率の達成」や「行政指導の回避」です。もちろん、それ自体は社会的な責任として重要です。しかし、制度対応の延長線上には、持続的な成果は生まれにくいのが現実です。
法定対応とは「外から求められた行動」、経営対応とは「内から生み出す行動」。この違いが、取り組みの持続力を決定づけます。大企業から中小企業まで、いろいろな企業を見てきた中で、障害者雇用を組織内で上手に進めているポイントを考察しました。
「雇用率を守るための雇用」は、目的が外にある
法定対応を目的にすると、企業の行動は「外部基準」に引きずられます。つまり、「行政に指摘されないように」「数字を報告できるように」という外向きの動機が中心になります。
この場合、採用や配置の判断が“形式的”になりやすく、
・本来の業務設計が十分でないまま採用される
・現場任せのフォローになり、上司が疲弊する
・雇用が続いても、職場全体の学びにつながらない
といった状況を招くことになります。
「雇うこと」が目的化してしまうと、雇用後の“意味づくり”が抜け落ちてしまうのです。
“点の取り組み”では、知が組織に蓄積されない
法定対応型の取り組みでは、担当者や現場の努力に依存しやすい傾向があります。担当者が異動すればノウハウが途切れ、同じ課題を繰り返す事例がよく見られます。
これは、組織として「知を共有する仕組み」がないことが原因です。障害者雇用を一つの「業務プロセス」や「人的資本戦略」として捉え、採用・配置・定着・育成の各ステップを“見える化”することで、再現性が生まれます。
制度対応では「担当者の頑張り」で回っている組織も、経営視点を取り入れることで「仕組みで動く組織」に変わっていくことができます。
成果を“経営語”で語ることにより、次の投資につなげる
法定雇用率を達成しても、経営会議で話題に上がらない、そんな企業は少なくありません。
なぜなら、「人事の取り組み」「CSRの一環」として捉えられ、経営にとってのリターン(生産性・リスク低減・組織文化の変革)として翻訳されていないからです。
経営は「理念」よりも「構造」で動きます。
たとえば、
・障害者雇用を通じて離職率が下がった
・メンタル不調の早期発見につながった
・チームのコミュニケーション改善が進んだ
こうした成果を経営指標の言葉で可視化できれば、障害者雇用は「社会貢献」ではなく「経営戦略」として位置づけることができます。
“法定対応”を超えて、“組織能力の開発”の視点をもつ
障害者雇用の本質は、「制度対応」ではなく「組織開発」です。雇用を通じて、社員一人ひとりのマネジメント力や関係性の質を高めることができれば、各部門の生産性向上、そして組織全体にも波及します。
つまり、法定対応を“入口”にして、「多様な人材を活かす力=組織能力」へと発展させられる視点があると、持続的な成果を上げる企業に近づくことができます。
障害者を「雇うこと」だけを見ているのか、それとも人材や組織全体を見ながら進めるのかで、障害者雇用だけでなく、組織づくりも大きく変わってくることにつながり、その選択が、企業の未来を分けます。
経営視点での“新しい評価軸”を持つ
「法定雇用率の達成」は、取り組みの“結果”を示す指標です。しかし、経営視点から見れば、それは“入口”であり、本当の成果は「組織がどれだけ変わったか」にあります。
では、その変化をどのように測ることができるのでしょうか。
“人的資本”としての変化を捉える
障害者雇用を経営に位置づけるうえで重要なのは、「どれだけ雇用率を達成しているか」ではなく、「どれだけ人材が育ったか」「どれだけ関係が変わったか」です。
たとえば次のような指標は、法定雇用率では見えない“人的資本の成果”を映し出します。
・障害のある社員の定着率や職務拡大の推移
・障害者雇用を通じて育った管理職の対話力・支援力
・チームの協働性や相談文化の浸透度
・障害者雇用を契機に見直された業務プロセスの改善率
これらはすべて組織の「内的な成長」を示すサインです。数字では表しづらい部分こそ、経営の持続性を左右する「見えない資産」といえます。
“配慮”を“仕組み”に変える
障害者雇用では、「障害者のために特別な対応をする」という個別的な配慮が重視されがちです。しかし、経営視点ではそれを「組織の仕組み」として定着させることが重要です。
障害者だけでなく、リーダーや管理職が障害者も含めた多様な人材のマネジメント力をあげるという視点をもつと、配慮を人材育成の仕組みに昇華することができます。
たとえば、
・業務マニュアルやチェックリストの整備
・上司向けの合理的配慮トレーニング
・人事データと連動した支援履歴の管理
などです。属人的な配慮を仕組み化することで再現性が生まれ、他の人材領域にも転用可能になります。
「一人のための工夫」が、「誰もが働きやすい制度」へと変えていくことができます。
経営に伝わる“成果の言語化”
現場が感じる「よくなった」という実感を、経営層が理解できる言葉に変えること。
それが、“経営会議で語られる障害者雇用”の第一歩です。
たとえば、
・「離職率の低下」=定着支援による採用コスト削減効果
・「社員の意識変化」=心理的安全性向上によるチームパフォーマンス改善
・「配置転換の工夫」=人的資本の最適配置モデルの実践
このように、経営が使う“成果の単語”に翻訳することで、障害者雇用は“社会的義務”から“経営投資”へと位置づけが変わります。数字の背後にある「変化の質」をどのように捉えるのかが重要となるでしょう。
法定雇用率は“入り口”でしかない
障害者雇用の取り組みを進めるとき、多くの企業はまず「法定雇用率の達成」を目標に掲げます。それは確かに、社会的責任を果たすための重要な第一歩です。しかし、その数字を“ゴール”とするか、“入り口”とするかで、組織の未来は大きく変わります。
法定雇用率を満たすことは、「制度を守る企業」としての評価にすぎません。本当に評価されるのは、制度を通じてどんな組織をつくったかです。
・社員同士の理解が深まり、心理的安全性が高まった
・マネジメント力が磨かれ、チームの生産性が上がった
・人材の多様性が、事業やサービスの新しい価値創出につながった
こうした変化こそが、法定雇用率の“先にある成果”であり、企業の持続的成長を支える「見えない資産」につながります。
障害者雇用を進める過程で、企業はさまざまな壁に直面します。それは、採用や配置の問題だけでなく、“関わり方”や“マネジメントの在り方”といった、組織文化そのものに関わる課題です。
だからこそ、障害者雇用は経営と人事の協働テーマであるべきです。「雇うこと」を目的にせず、「どう活かすか」「どう成長するか」を考えることで、組織は一人ひとりの違いを価値に変える力を身につけていくことができます。
障害者を含めた多様な人材が働きやすい環境を整えることは、結果として「誰もが成果を出せる職場」をつくることにつながります。
経営の視点から見れば、障害者雇用とは “社会課題の解決”であり、“組織課題の解決”でもある。この二つを結びつけることが、次の時代の企業価値を生み出す鍵になります。
そしてその起点は、「法定対応」から「経営対応」へと発想を転換することです。
いま一度、自社の障害者雇用の“成果指標”を見直してみませんか。
障害者雇用ドットコムでは、「数字を超えた成果」を経営の言葉で設計するための支援・コンサルティングを行っています。現場の定着支援から経営企画層の戦略設計まで、“組織を変える障害者雇用”の実践事例を紹介しています。
NewsPicksコラム:「法定雇用率はゴールか、スタートか?──制度遵守から“戦略”へ」を読む










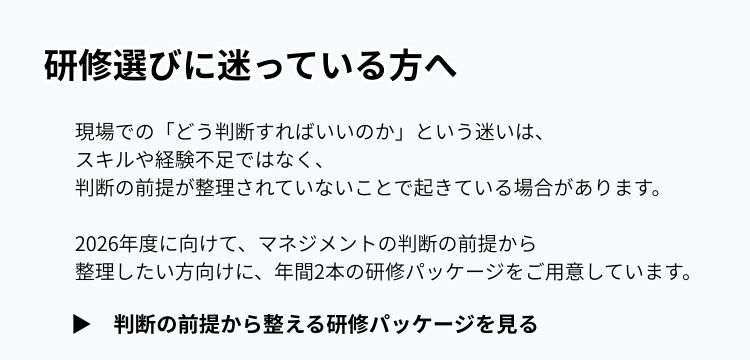















0コメント