「最近、自分の仕事がうまく回っていない気がする」「サポートに追われて、気づいたら一日が終わっていた」そんな感覚を抱いている方はいませんか?
障害者とともに働く現場では、“支える側”としての役割を担う社員が少なくありません。そのなかで、支援に力を注ぐあまり、自分の本来の業務が後回しになってしまっているケースも多く見受けられます。
真面目で、思いやりのある人ほどこの状態に陥りやすく、「自分の時間がなくても仕方ない」「自分の仕事より大事なことがある」と思い込んでしまうこともあるでしょう。しかし、それは善意が裏目に出ている状態かもしれません。
配慮しようとする気持ちは素晴らしいものです。けれども、それが積み重なることで、「役割の境界」が曖昧になり、本人もチームも疲弊してしまうという“誤解に基づく状態”が生まれてしまいます。
このコラムでは、「なぜ、自分の仕事がうまく進まなくなったのか?」という原因を整理し、明日から少しでも前向きに動けるヒントをお届けします。あなた自身が、無理をせず健やかに働きながら、障害のある方とよい関係を築いていくために──。一緒に、立ち止まって考えてみましょう。
動画で見る
Podcastできく
【原因の整理】──よくある3つのパターン
「自分の仕事が後回しになっている」「気がつけばサポート役に徹していた」そんな状態に陥ってしまう背景には、いくつかの共通したパターンがあります。ここでは、よく見られる3つの要因を紹介します。
そのいずれも、善意や責任感がベースにあるからこそ起こるものです。でも、忘れてはならないのは、 障害者雇用は「支援の場」ではなく「雇用の場」、つまり“職場”だということです。お互いに働くことが前提であり、社員として役割と責任を果たす関係性が基本です。その原点に立ち返りながら、自分の仕事が後回しになる原因を見つめ直してください。
原因1:「いい人でいよう」として抱え込みすぎている
「困っていそうだから代わりにやってあげよう」「言いづらそうだから、代弁してあげよう」そんな“やさしさ”が積み重なると、いつの間にか「支援」が目的になってしまいがちです。
その結果、障害者社員と対等な“仕事のパートナー”として関わる意識が薄れ、自分の業務まで圧迫されていくことになりがちです。
✅対策:役割分担の棚卸し・見直し
「これは本来、誰の仕事なのか?」 「サポートが業務の主体を奪っていないか?」 といった視点で、支援と業務の境界線を見直すことが必要です。
原因2:職場に「配慮=特別扱い」という空気がある
「そこまでやる必要ある?」「なんか腫れ物扱いしてない?」そんな声や空気感が、知らず知らずのうちに現場に漂っていることがあります。また、責任感が強い人は、自分ひとりでそのことを抱え込んでしまい、チームの中で“浮いた存在”になってしまい、孤立感を抱えやすいことも多く見られます。
本来、職場での合理的配慮は“特別扱い”ではなく、“働きやすくするための工夫”です。チームで共有し合いながら、全員で働きやすい環境をつくっていくことが理想です。
✅対策:チームでの共有と合意形成
支援や配慮の内容を、上司や同僚と共有し、職場全体の理解を得ましょう。合意を得たうえで支援に取り組むことで、支援が“属人的”なものにならず、チームの方針として機能します。
原因3:「どう関わっていいか分からない」まま対応が後手に
精神障害や発達障害など、外からは見えにくい特性の場合、どう接してよいか分からず戸惑う人も多いでしょう。
「これは聞いていいのかな?」「どこまで伝えていいんだろう?」と迷っているうちに、対応が後手に回ってしまい、本人にも自分にもストレスがかかる結果になってしまいがちです。このような状況は、「障害=特別な知識が必要」と構えてしまうことから生まれます。でも本当は、“障害名”を知るよりも、「今、何が難しいのか」「何があればやりやすくなるのか」を共有し合うことのほうが大切です。
✅対策:障害名ではなく“困りごとベース”で考える
「何ができないか」よりも、「どんな場面で困っているか」から考えることをはじめてください。 “業務上の困りごと”にフォーカスすることで、仕事の前提である対等な関係性を保ちながら関わることができます。このように、「やさしさ」や「遠慮」から始まった行動が、結果的に職場でのバランスを崩すことがあります。でも、それは“やり方”の問題であり、こうしたズレを整えることによって解決できます。
まとめ
「自分の仕事ができていない」
「ちゃんとサポートできていない気がする」
このように感じていたとしても、それは努力不足ということではありません。むしろ、“配慮しなければ”という思いの強さが、本来の仕事の目的や関係性の軸をぼやけさせてしまった結果とも言えます
ここで、もう一度立ち返りたい原則があります。それは、障害者雇用は「配慮や支援」ではなく、「仕事をするための雇用関係」であるということです。障害者も“雇用される一員”として職場に加わっており、それぞれに与えられた役割・責任のもとで働くことが前提です。誰かのサポートだけが業務になってしまっているのであれば、自分の業務にきちんと取り組めるようにすることが、職場全体への貢献になります。
業務や関係性の中で「どうしたらうまくいくか」をともに考え、ともに成長するプロセスです。もし、今、負担を感じているのであれば、少し整理するだけで、景色が変わってきます。
次のことを考えてみるとよいでしょう。
・今、自分がどんな支援をしているのか
・その支援は、本人の業務遂行につながっているか
・支援によって、自分の仕事にどんな影響が出ているか
・本来、支援すべき人は自分だけなのか(職場全体での体制が必要では?)
こうした点をいったん立ち止まって整理することが、状況を前向きに動かす第一歩です。
職場全体で考える「関わり方」へとシフトしていくこと、そして、障害者雇用を“やさしさ”だけで終わらせない、本質的な共生につながります。
障害者雇用の現場で、「どのように関わればいいのか分からない」 「サポートと業務のバランスが難しい」 そんな悩みを抱えているのは、あなただけではありません。実はこのような声は、多くの職場で共通して聞かれる現場課題です。
制度や理念ではなく、日々のやりとりや関係性の中で生じる“実務のギャップ”こそが、障害者雇用を難しくしている大きな要因となることも少なくありません。こうした“見えにくい現場の悩み”に対応できるための現場実例とマネジメント視点をもとに構成したオンライン講座があります。関心のある方は、こちらから。

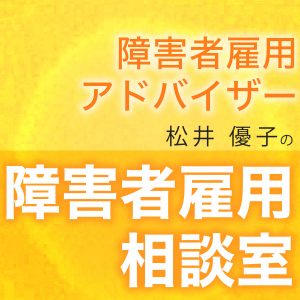









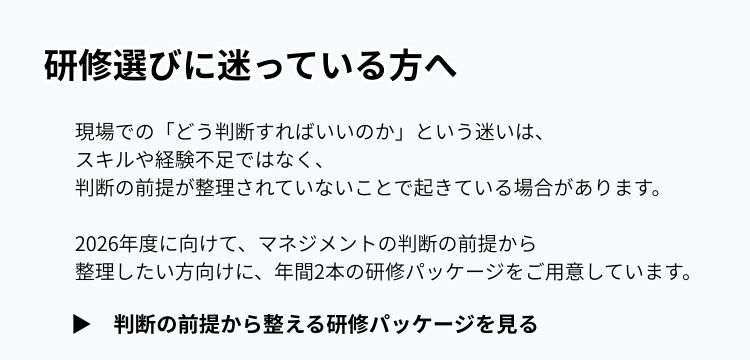















0コメント