「障害者と一緒に働くことになった…正直、ちょっと不安です。」
これは、現場の多くの人が心の中で感じている率直な声です。けれど、その“不安”の正体をたずねてみると、「なんとなく…」「どう接したらいいのか分からない気がする」といった、あいまいな答えが返ってくることが少なくありません。
実はこうした漠然とした不安は、珍しいことではなく、誰しもが感じ得る自然な反応です。人は「知らないこと」「経験したことがないこと」に対して、本能的に不安や警戒心を抱くもの。とくに、“障害”というテーマは、日常生活のなかで関わる機会が少ない人にとっては、どう扱えばいいのか分からず、余計に距離を感じてしまうものだからです。
でも、不安という感情は決して悪者ではありません。それは、あなたが「相手との関係を大切にしたい」と思っているからこそ生まれる、前向きなサインでもあります。そして、その感情をそのままにせず、「私はなにが不安なんだろう?」と立ち止まって言葉にしてみることが、よりよい関係づくりへの第一歩になります。
今回は、そんな“不安”を具体的に見つめ直し、言語化してみることの重要性について、一緒に考えてみたいと思います。
動画で見る
Podcastできく
よくある“不安”のパターンを整理してみる
実際に職場でよく聞かれる「不安」の声には、次のようなものがあります。
「どのように接したらいいかわからない」
最も多く聞かれるのがこの声です。 「傷つけないようにしないと…」という気持ちから、逆に遠慮しすぎて距離をとってしまうケースも少なくありません。とくに、どんな配慮が必要なのか、何を聞いてよくて何を聞くと失礼なのか、判断に迷ってしまうという声が多く見られます。
「特別扱いしなきゃいけないのか?」
「周囲と同じように接するべきなのか、それとも違う配慮が必要なのか」——このバランスに戸惑う人も多くいます。 一部では、「特別扱いしていたら他のメンバーとの公平性に欠けるのでは?」というモヤモヤを抱えているケースもあります。
「仕事を一緒に進められるのか心配」
「どこまでの業務を任せていいのか分からない」「フォローが大変になるのでは?」といった声もよく聞かれます。これは、障害者のスキルや特性を知らない状態で、“戦力にならないのでは”という先入観が先行していることに起因しています。
「関わり方を間違えてしまったらどうしよう」
善意で関わろうとしたことが逆効果になるのでは、という不安です。 「言葉づかいや態度に配慮が足りなかったら責任を感じる」「配慮したつもりが“過干渉”に見えてしまうのでは?」と、正解がわからず戸惑ってしまうことがあります。
「周囲の負担が増えるのでは?」
これはチームや部署全体の視点での不安です。 「フォローが必要になったとき、他のメンバーにしわ寄せがいくのではないか」「仕事の進行が遅れてしまうのでは」といった懸念から、不安を感じる人も少なくありません。
こうして見てみると、不安の多くは「知らない」「わからない」ことによって生まれていることがわかります。だからこそ、こうした声を言葉にして整理し、共通認識として社内で共有していくことがとても大切なのです。
なぜ“言語化”することが大事なのか?
人が感じる不安の多くは、「分からないこと」によって生まれます。そしてその「分からない」という感情を、そのままにしておくと、不安はどんどん膨らんでいきます。「なんとなくモヤモヤする」「なぜか気が重い」——その状態では、自分が何に困っているのか、どうすれば楽になるのかも見えません。だからこそ、不安を感じたときは、それをいったん立ち止まって「言葉にしてみる」ことがとても重要になります。
例えば、「どう接したらいいかわからない」と感じたとします。 これは言い換えれば、「どんな配慮が必要なのかを知らない」「これまで関わった経験がなく、接し方の引き出しが少ない」という状態です。 つまり、“自分が何を知らないか”を認識することができれば、その「知らないこと」を学べばいい、という具体的なアクションにつながっていきます。
また、「仕事を一緒に進められるのか不安」という場合も、よくよく言葉を掘り下げていくと、「どんな業務を担当するのか分からない」「自分がどんな役割を担えばいいか明確でない」というように、構造的な課題が見えてくることもあります。
言語化することで、不安は“曖昧な感情”から“具体的な問い”へと変わります。 問いに変われば、答えを探すことができます。 誰かに相談することもできるし、必要な情報を集めることもできる。つまり、不安の正体が見えることで、対処の選択肢が広がるのです。
そして、何より大切なのは、「不安があること自体は悪いことではない」ということ。それを丁寧に見つめ直し、言葉にしていくことこそが、よりよいコミュニケーションや関係づくりの第一歩になります。
不安を解く第一歩:知識と対話で変わるもの
不安の正体が見えてきたら、次はそれをどう解いていくかを考えていきます。 多くの場合、不安を和らげる鍵は「知識」と「対話」にあります。
接し方に“正解”はある?
「どう接すればいいか分からない」という不安の多くは、誤解や思い込みに起因しています。 「障害があるから配慮をしなければならない。」「特別な接し方が必要。」と構えてしまいがちですが、障害者雇用では同僚、部下として“普通に接する”ものです。むしろ、過度な配慮や過干渉の方が、相手との距離を生んでしまうことがあります。
もちろん、必要な配慮やサポートは人それぞれ異なりますが、まずは一人の同僚として、自然な関わり方を意識することが基本です。
支援が必要な場面と必要でない場面、見分けるポイント
とはいえ、「どこまで手助けすればいいのか」は迷うポイントかもしれません。 ここで大切なのは、「相手の特性を理解したうえで、必要なときに必要な支援をする」という視点です。
支援が必要かどうかの判断に迷ったら、まずは“本人に聞いてみる”ことをしてください。「何か困っていることはありますか?」「どのあたりがやりにくいですか?」と丁寧にたずねるだけでも、関係性は大きく変わっていきます。相手のことを“理解しようとする姿勢”が、信頼関係を築く第一歩になります。
困ったら、誰に聞けばいい?
それでも障害者への対応で迷ったり、困ることが出てきたときは、一人で抱え込まずに相談してください。会社によっては、相談窓口や支援体制を整備していることがあります。例えば、人事部やD&I推進で、障害者雇用の担当者がいるかもしれません。
もし、社内にいないのであれば、地域障害者職業センターのカウンセラーやジョブコーチ、障害者を採用した支援機関や人材紹介会社などの担当者に聞くこともできます。
相談することは、決して自分がダメなわけではありません。適切な人に相談することは、必要な支援を早く届けられたり、問題解決につながります。結果的に職場全体で働きやすさを実現することになります。はじめから完璧である必要はありません。まずは「知ろうとすること」「話そうとすること」から、少しずつ試していけば大丈夫です。
まとめ
障害者と働くことに不安を感じるのは、決して特別なことではありません。むしろ、それは「どう関わるのがいいのか」「相手の力を活かすにはどうすればいいのか」と、真剣に向き合おうとしている姿勢です。
その不安を、ただの“気持ち”のままにせず、丁寧に言葉にしてみる。「何が分からないのか」を見つけ、「誰かに相談していい」と思う。このようなことから、職場やそこで働く障害者にとって、安心できる土台が生まれていきます。
障害者雇用は、決して特別な世界ではありません。「知らない」から「少し知っている」に変わるだけで、見える景色が変わってきます。配慮や遠慮、「こうしなければならない」とガチガチになっていると、相手も構えてしまいます。「ちょっと話してみる」「こんな風にすると働きやすくなるかも…」と対話が始まり、それが回り始めると少しずつよくなっていきます。
もし今、不安や戸惑いを感じるのであれば、障害者雇用に関するオンライン講座を受けてみてください。障害者とどのように関わるとよいのか、どんな強みを活かせるのか、現場で役立つ知識と実践ヒントが学べる内容になっています。障害者雇用の「知らない」を、「知っている」「できるかも」に変えるきっかけになるはずです。

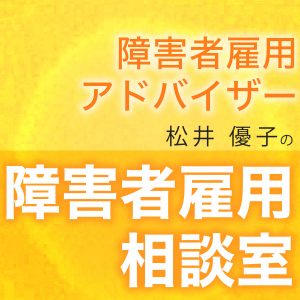
























0コメント