「相談窓口はあるけれど、社員が使ってくれない。」
これは多くの企業から聞かれる声です。せっかく法制度に基づいて窓口を設置しても、「相談しても何も変わらない」「逆に自分の評価に響くのでは」といった不安から、社員は声を上げられずにいます。
ようやく寄せられた相談も、担当者が一人で抱え込み、解決に至らないまま形だけの対応に終わることも少なくありません。その結果、相談者は不満や不信感を募らせ、現場では人材の離職やメンタル不調が表面化します。
そして対応に追われる人事部や窓口担当者自身も疲弊し、組織全体に負の連鎖が広がっています。
YouTube
Podcast
データが示す「制度はあるが機能しない」現状
「相談窓口を設置しても、実際には社員が利用していない」
この現状は、調査結果にも表れています。厚生労働省の令和5年度調査によると、民間企業の従業員のうち 65.6%が『相談自体がムダだと感じている』 と答えています。
また、人事院が令和6年に行った調査では、公務員の 52.2%が『相談しても解決しないと思った』 と回答しており、官民を問わず“相談の無力感”が広がっていることがわかります。
さらに、厚労省の同調査では、企業の 6.1%が『相談者に不利益な取り扱いをした』 と報告しており、相談そのものが逆効果となるリスクさえ存在しています。
一方で、人事労務担当者500名を対象とした民間調査(令和4年度)では、半数以上が「従業員は相談窓口を活用していない」と回答しています。つまり、現場では「制度はあるが機能していない」という典型的な構図が浮かび上がります。
相談できない社員は不満やストレスを抱え込み、やがてメンタル不調や退職につながり、組織にとって大きな損失を生みかねません。窓口担当者自身も孤立し、過度の負担を抱えるケースが多く、まさに「相談できないこと」が次のリスクを生む悪循環を作り出しているといえます。
よくある失敗事例
ある企業で、障害のある社員が「業務上の配慮」を求めて人事の相談窓口を訪れました。しかし、対応は形式的で、現場に正しく伝わらないまま放置され、本人は孤立感を深めて退職してしまいました。
別のケースでは、パワハラを訴えた社員の相談内容が加害者に伝わり、報復的に人事評価を下げられるという逆効果が生じました。また、相談窓口の担当者自身が、社員から寄せられる切実な声を一人で抱え込み、感情的に疲弊し、最終的には休職せざるを得なくなった事例もあります。
こうした「誰も悪意はないのに、制度が機能しない」失敗は珍しくありません。データが示すとおり、相談者は「どうせ変わらない」と諦め、組織は人材の離職や信頼低下という代償を払っています。制度を整えただけでは、社員の安心や信頼は得られないのです。
あなたの組織ではどうですか?
では、あなたの会社ではどうでしょうか。相談窓口は「ある」だけで満足していませんか?社員は本当に安心して利用できているでしょうか?
相談を受けても「形式的な対応」で終わり、解決につながらないまま、問題が水面下で膨らんでいる可能性はないでしょうか。もし「うちの社員は特に声を上げていないから大丈夫」と感じているとしたら、それこそ危険のサインです。
声を上げられない背景には、不信感や不安感が潜んでいます。制度を設けても、使われなければ意味がありません。むしろ“相談できないこと”が次のリスクを生み出してしまうのです。
解決にむけて見直すべき3つの方向性
いま企業に求められているのは、相談窓口を「設置すること」ではなく、「社員が安心して使えるように機能させること」です。
そのためには、次のことが必要です。
1.まず相談しても不利益を受けないという“心理的安全性”を確保すること。
2.上司・人事・外部機関など複数のルートを用意し、社員が選べる状態にすること。
3.窓口担当者が「聴く・整理する・つなぐ」役割を果たせるよう、教育や支援体制を整えること。
最近ではAIによる一次対応や匿名相談の仕組みなど、新しい選択肢も出てきています。重要なのは、相談を「形骸化した制度」から「社員に信頼される仕組み」に変えていく視点です。
こうした“相談できない”現状をどう変えていけばよいのか。制度が形骸化する理由や、機能させるための具体的な工夫については、一度立ち止まって整理する必要があります。
社員が安心して使える仕組みへ─AI活用の提案
AIを活用した新しい相談窓口 の導入支援も行っています。匿名での一次相談や24時間対応など、社員が安心して声を届けられる仕組みをAIが補完することで、窓口担当者の負担を減らしつつ、相談体制を強化することが可能です。
実際に導入を検討される企業様には、デモ体験や活用事例のご紹介 も行っています。「相談窓口を形骸化させたくない」「AIを活用して社員の声をもっと拾いたい」とお考えでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

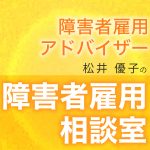









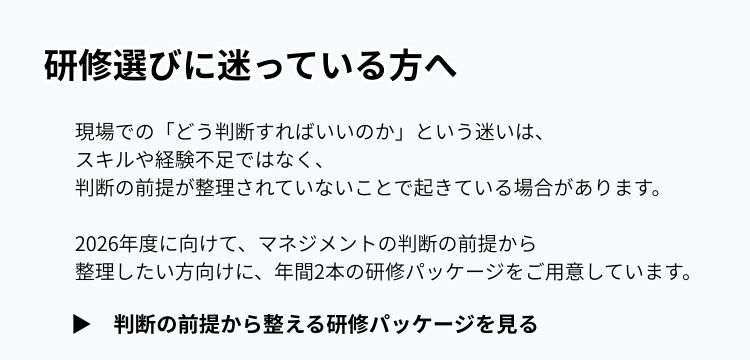















0コメント