「これくらい普通にできるでしょ」
「なんでこんな簡単なことが伝わらないの?」
障害のある社員と一緒に働く中で、そんなふうに感じてしまった経験はありませんか?
もちろん、表立って怒ることはないし、できるだけ冷静に対応している。それでも心の中では、じわじわとイライラが積もっていく。そして、ふとした瞬間に「自分、心が狭いのかな…」「こんなことで腹を立てるなんて…」と、イライラしてしまう自分を責めてしまうこともあるかもしれません。
でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。そのイライラの正体、もしかすると「相手が悪い」のではなく、“こちらの期待値”に原因があるのかもしれません。「これくらいできるはず」「これくらい分かってくれるだろう」という“無意識の基準”が、知らず知らずのうちに、現実とのギャップを生み出している可能性があります。
今回は、「そもそも求めている業務レベルは適切か?」という視点から、イライラの原因を見直していきます。相手のためだけでなく、自分自身が気持ちよく働くためにも、「期待値の調整」は大切なステップとなります。一緒に、整理してみましょう。
動画で見る
Podcastで聞く
その“当たり前”は、誰にとっての基準?
「これくらい、普通はできるよね?」 「社会人なんだから、この程度はわかっているはず」そう思って任せた業務が、想像以上にうまく進まなかったり、何度説明しても伝わらなかったりすることがあります。 そんなとき、私たちはつい“できないこと”に目を向けがちです。
けれども、考えてみてください。その「当たり前」は、誰にとっての基準でしょうか?
あなたにとって自然にできることでも、相手にとっては高すぎるハードルになっている場合があります。特に精神障害や発達障害など、外からは見えにくい困難を抱えている人の場合、「なぜできないのか」が理解しにくいことも多くあります。
例えば…
・複数の指示を一度に処理するのが難しい
・曖昧な表現や臨機応変な対応が苦手
・場の空気を読んで動く、といった“暗黙の了解”が理解できない
こうした特性がある場合、「できない」のは本人の意欲や努力が足りないからではないことがあります。 求めている“業務レベル”そのものが、今の本人の力と合っていない可能性があるかもしれません。また、 「できる」能力やスキルがあったとしても、指示の方法や伝え方によっては理解が難しいこともあります。
「今、その人に何をどのレベルで求めているか」が明確になっているでしょうか。イライラや不信感の背景には、この“見えない期待値のズレ”が潜んでいることがあります。それに気づくことができれば、解決の糸口が見つかります。
業務の“3つの視点”で見直す
「期待していたように動いてくれない」 「こちらの意図がなかなか伝わらない」 そんなもどかしさを感じたときに役立つのが、“業務そのもの”を整理して見直す視点です。
ただ単に「できる・できない」で判断するのではなく、 以下の3つの切り口で整理することで、期待値とのズレを解消するヒントが見えてきます。
業務の内容──本当にこのタスクが本人に必要か?
よくあるのが、 「空いていたから任せた」 「誰かがやらなきゃいけないからとりあえず」 という理由で業務を振ってしまっているケース。
しかしその業務、本当にその人が担うべきものなのでしょうか? タスクを細かく分解してみると、「これは別の人が担う方が自然」「この部分だけなら任せられる」ということもよくあります。
以下の点を見直すことができるかもしれません。
・業務の“目的”を見失っていないか?
・「一連の仕事」ではなく「部分的な役割」にできないか?
業務のレベル──求めるスピード、精度、柔軟性は?
「正確に」「すぐに」「空気を読んで」 ……といった“見えない条件”が、無意識のうちに要求水準として加わっていることがあります。
例えば、
・指示があいまいなまま放置してしまっている
・臨機応変な判断を期待している
・他の社員と同じ水準でスピードや成果を求めている
こうした「見えない業務の期待水準」は、特に精神・発達障害のある社員にとって非常に高いハードルになることがあります。一方で、求めている“基準”を明文化できると、とても判断しやすくなります。場合によっては、判断力や処理スピードに対する期待が過剰になっていることもあるので、今の業務を担っている人がどれくらいなのかを基準としてもっておくとよいでしょう。
業務の支援──「個人の親切」が、組織の基準になるとき
本人に任せきりにしていたり、逆に支援しすぎていたり…。「支援と業務」の線引きがあいまいになると、どちらにとってもストレスになります。
合理的配慮は「やさしさ」ではなく、業務遂行を可能にする“環境の工夫”です。業務のやり方を少し変える、サポート体制を一部組み込むなど、チームとして整えられた対応が求められます。
特に注意したいのは、「属人的な支援」が常態化していないかという点です。ある担当者が善意で手厚くサポートした結果、それが“その人にとっての当たり前”となってしまい、次に別の担当者に代わった際に、「前はやってくれたのに」と不満や混乱が生じることがあります。
例えば、ある社員が「毎朝、声をかけてもらわないと仕事を始められない」という状況があったとします。前任者が自然に声をかけていた場合、それは“配慮”というより“個人的な対応”だと考えられます。しかし、それが本人の中で「職場のルール」として定着してしまうと、次の担当者が同じようにしないことに不満が生まれ、「冷たい」「わかってくれない」と感じられてしまうことがあります。
そのためチームとして、対応方針が共有されているか? 誰か一人の“好意”に依存した関わり方になっていないか?という点を意識しておくことが大切です。支援の基準は、組織としての共通認識に基づいてこそ、持続的かつ公平な運用が可能になります。
属人的な関わりが続くと、支援を受ける側も提供する側も、期待と現実のズレに苦しむことになりかねません。だからこそ、「どこまでが業務で、どこからがサポートか?」をチーム全体で共有し、支援が個人に偏らない仕組みをつくることが重要となります。
業務を“タスクの中身・レベル・支援の仕方”という3つの視点で分解することで、「なぜうまくいかないのか」が、感情論ではなく構造として見えてくるようになります。
次のセクションでは、その見直しをふまえて、「できないこと」との向き合い方をどう変えていけるかを整理していきます。
「できない」ことへの向き合い方を変える
障害のある社員が「業務をうまくこなせない」とき、 私たちはつい、“能力の問題”として捉えてしまいがちです。
でも本当にそうでしょうか?実は、「業務のやり方が合っていない」「指示の伝え方がわかりにくい」「そもそも求められている水準が高すぎる」……といった要因によって、“できないように見えている”だけというケースも少なくありません。
「できない=ダメ」ではなく、「ズレ=調整ポイント」
私たち自身にも、得意不得意があります。例えば、人前で話すのが苦手な人に司会を任せるのは、苦痛でしょう。同じように、ある人にとっては簡単なことでも、別の人にとっては工夫が必要なこともあります。
「できない=能力が低い」ではなく、「やり方が合っていない」だけかもしれないという視点を持つことで、 関わり方が変わることがあります。
「求めること」と「任せること」はイコールではない
つい「こうあってほしい」「これくらいやってほしい」と、無意識の期待を重ねてしまうことがあります。けれども、それが現実とかけ離れていた場合、イライラが募るだけでなく、本人も「うまく役に立てていないのでは」と自己肯定感を失い、悪循環に陥ってしまいます。
だからこそ大切なのは、「求めること(理想)」と「任せること(現実)」の間にある“差”をきちんと認識し、そのギャップをどう埋めていくかをチームで考えることです。
特に発達障害のある方の場合、「できること」と「できないこと」の差がとても大きいという特性がよく見られます。例えば、ある業務では100の成果を出せる力があるとします。そうすると、まわりは「これができるのだから、他の業務も同じようにできるはず」と思いがちです。しかし実際には、別の業務では60や70程度の力しか発揮できないことも少なくありません。
この“ギャップ”こそが、しばしば誤解を生む要因になります。
「あれだけできる人なのに、なぜこれができないの?」「本人のやる気がないのでは?」「配慮しすぎているのでは?」そんな声があがる背景には、この“ばらつき”が理解されていないことがあります。
すべてを均一にこなせることを前提とせず、「どの業務なら力を発揮しやすいのか」「どこで苦手が出やすいのか」を丁寧に把握することが、本人の強みを活かしつつ現実的な任せ方をする鍵になります。
「できる」部分だけを見て、それを“基準”にしてしまうのではなく、「できること」「難しいこと」の両方を含めてその人の特性と捉える——この視点の転換が、健全な期待値の調整につながります。
チームで調整する力が、成果につながる
誰か一人に頑張らせるのではなく、 「どうすればこの業務を遂行できるか」をチームで考える文化がある職場は、障害のある社員にとっても、そうでない社員にとっても働きやすい環境になります。
イライラを減らすことは、ただの感情コントロールではなく、 期待と現実をすり合わせ、チームの生産性を高めるマネジメント行為でもあります。
「できないこと」に目を向けるのではなく、 「どうすればできる形になるか」を一緒に考える。その発想の転換こそが、職場の空気を変え、 自分自身の働き方にも余裕を生み出してくれるはずです。
まとめ
「これくらいできるはず。」「なんで伝わらないんだろう。」 そんなふうに感じてしまうとき、私たちは無意識のうちに「自分の基準」で相手を見てしまっています。
けれども、その基準は本当に、相手にとっても“適切”なものでしょうか?
次の点を見直すことは、 「できない」のではなく「合っていない」ことに気づくきっかけになります。
✔ 今任せている業務は、本人の特性やスキルに合っていますか?
✔ 期待している“成果”や“スピード”は、誰の基準ですか?
✔ その業務、本当にその人が担う必要がありますか?
✔ 支援体制は一人に偏っていませんか?チームで共有できていますか?
これらを一つひとつ言語化してみるだけで、 イライラの原因が「本人」ではなく、“関係性の設計や期待値のすれ違い”にあることが見えてくるかもしれません。

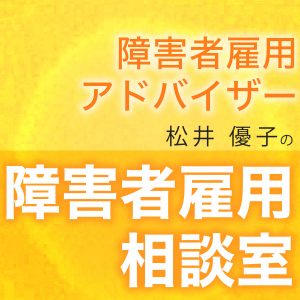









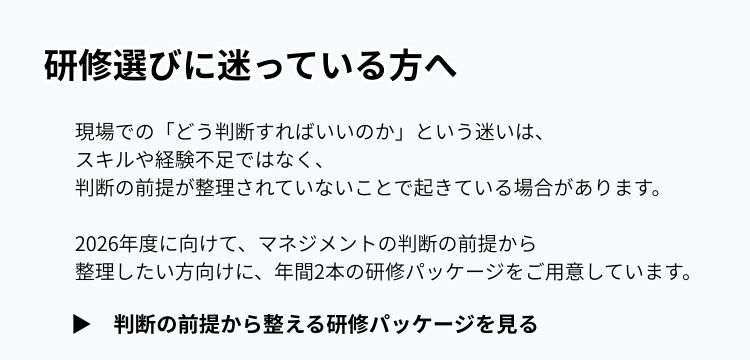















0コメント