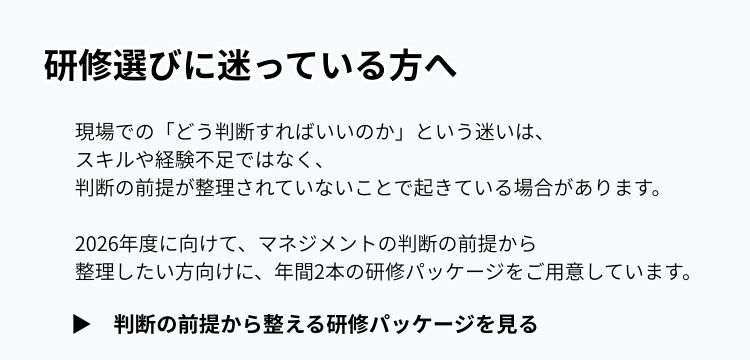会議が決まらない会社に共通する5つの構造問題
会議が決まらない原因は、個人の能力ではなく、組織の判断構造にあるかもしれません。本記事では、会議が止まる会社に共通する5つの構造要因を整理します。 会議が増えているのに、なぜ決まらないのか 会議の回数は増えているのに、なかなか物事が決まらない。 何度も議論しているのに、前に進んでいる実感がない。 論点は整理され、懸念点も共有され、反対も出ていない。 それでも最後は――「一旦、持ち帰ります。」 「次回までに確認します。」そんな形で終わっていないでしょうか。...